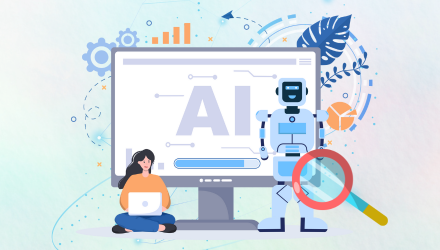BIツール vs. 生成AI?両立して実現するAI時代のデータ活用とは
企業におけるデータ活用が進む中、BIツールはデータの可視化や分析を簡単に行える手段として定着してきました。多岐にわたるビジネスデータを集約し、グラフやダッシュボードを通じて直感的に把握できるその機能は、日々の業務改善や意思決定を大きく支援しています。しかし、近年、生成AIの目覚ましい隆盛は、従来のBIツールでは得られなかった新たな可能性を提示し、データ活用のあり方そのものを変えつつあります。
本コラムでは、データ活用の現場でいま最も注目されるBIツールと生成AI、それぞれの特性や最適な使い分け方を整理していきます。
![]() Shinnosuke Yamamoto -読み終わるまで4分
Shinnosuke Yamamoto -読み終わるまで4分
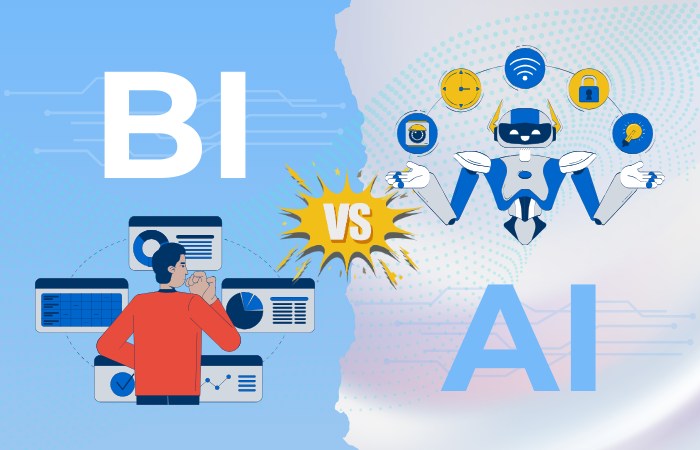
データ活用における生成AIの台頭
企業における生成AIの普及に伴い、データ活用の現場でもその可能性に注目が集まっています。従来、ビジネスユーザーの分析ニーズを支えていたBIツールでは対応が難しかった課題に対し、生成AIが新たな突破口となることが期待されています。
BIツールが抱えるデータ活用の課題
従来のBIツールは、売上推移や在庫状況、顧客動向といったビジネスの主要指標をダッシュボード上で可視化し、レポーティングを行うといった定型的な分析においてその真価を発揮してきました。しかし、膨大かつ複雑なデータセットを扱う際には、その前処理やデータクレンジングに多大な時間と手間がかかるという課題が常に付きまといます。データの形式が不揃いであったり、重複や欠損が含まれていたりする場合、専門的なスキルを持つ担当者が多くの工数を費やして手動で調整する必要があり、分析結果を導き出すまでにボトルネックとなりがちです。
加えて、BIツールはあらかじめ設定された指標やグラフをベースとするため、新しいパターンや未知のインサイトを探索するには、限界があります。関連するデータソースをどのように結びつけ、どのような視点で可視化すれば新たな発見があるかという設計自体が重要となるため、運用目的や要件定義が曖昧なまま導入を進めてしまうと、期待したほどの分析効果が得られず、結果としてダッシュボードが形骸化してしまう例も見受けられます。
生成AIによるデータ活用の可能性
生成AIの技術進歩はとどまるところを知らず、人間のアイデアや知識に加えてAIが生み出す情報を取り入れたデータ利活用が急速に広がりを見せています。これは単なる効率化にとどまらず、これまで不可能とされてきた領域でのデータ活用を可能にするものです。
近年、生成AIが、企業のマーケティング、製品開発、顧客サポートなど、さまざまな業界で具体的な活用事例を生み出し始めています。この波はデータ分析の世界にも大きなインパクトを与えており、専門的な知識を持たないビジネスユーザーでも、自然言語で問いかけるだけで社内の膨大なデータ資産を瞬時に検索し、必要な情報を導き出すことが可能になりました。生成AIが自動でデータベースクエリを生成・実行することで、データの抽出作業は大幅に効率化され、これまでアクセスが困難だったデータからでも隠れたパターンや新たな発見を得られるようになりました。
BIツールと生成AIの使い分け
すべてのデータ分析に生成AIを使うのが最適解というわけではありません。企業のデータ活用を最大限に加速させるためには、BIツールと生成AI、それぞれの得意領域を深く理解した上で、目的に応じた適切な使い分けを行うことが極めて重要です。
BIツールが適しているケース:定期・定型
BIツールは、日々のビジネスオペレーションにおいて定型的に確認すべき指標を高速かつ簡潔に可視化する分野で特に有効です。例えば、月次の売上推移、週ごとの在庫の増減、ウェブサイトのアクセス状況、製造ラインのログ監視や品質管理、部門別コストの分析など、安定したデータソースから継続的に抽出されるKPI(重要業績評価指標)をモニタリングする用途に最適です。
ダッシュボード上で過去データを様々な切り口で俯瞰し、重要なKPIや関連指標に異常がないかをチェックすることで、日常的な業務改善や迅速な意思決定を支援します。
生成AIが適しているケース:クイック・臨機応変
生成AIは、データから導くことができる傾向やインサイトをクイックに言語化し、利用者に示唆を与えることが可能です。従来の分析手法では、統計分析の結果やBIツールでの可視化の結果をどう解釈するかは人間に委ねられていました。生成AIは自然言語処理の技術によってデータの解釈を言葉で説明します。利用者である人間にとって、スキルに依存せずクイックにデータの分析結果を理解することができます。
また、データを使いたい利用者の関心はその時々で変化します。言語理解によって利用者が求めるデータを探索し、求める分析手法でデータから知見を引き出すことができる生成AIは、分析対象が固定化されるBIツールとは対象に臨機応変かつリアルタイムにデータを活用することができます。
BIツール×生成AIでデータ活用を加速
BIツールと生成AIは、決してどちらか一方を選択すべきライバルではありません。むしろ、それぞれの強みを融合させることで、データが持つ潜在的な価値をこれまで以上に効率的かつ深く探求し、ビジネスに還元することが可能になります。

生成AIで見つけた発見をBIツールで表現する
先に紹介したように、BIツールと生成AIツールを利用シーンによって使い分けることが重要です。一方、BIツールと生成AIを融合するという考え方もあります。
生成AIが見つけた深層的な洞察や、複雑なデータ間の隠れたパターンは、従来の形式では理解しにくい場合があります。そこで、その結果を視覚的に分かりやすいBIツールのダッシュボード上に落とし込むことで、データの全体像を多様な視点から直感的に把握することが可能になります。例えば、BIツールが得意とするグラフ表現と合わせて、どのような傾向が見られるのか、どのような発見があったのかのサマリを文章でダッシュボード内で表現することが考えられます。
こうしたAIが生成した知見を組み込んだダッシュボードは、専門の分析担当者だけでなく、時間のない経営層や、データ分析に不慣れな現場担当者にも分かりやすい形で情報を提供し、全社的な業務改善や迅速な意思決定につながります。
共通してデータ基盤の整備が重要
BIツール・生成AIを活用していくうえで、その真価を最大限に引き出すためには、まず何よりも強固なデータ基盤を整備することが大前提となります。どのような優れたツールを導入したとしても、その上に流れるデータが品質不良であったり、形式の不一致を含んでいたりする場合、正確な分析結果を得るのは極めて困難です。これは、誤った意思決定やナレッジの分散、さらにはビジネスチャンスの損失につながりかねません。
社内外の各種業務システム(CRM、ERP、SFAなど)や、ウェブサイト、IoTデバイス、外部データサービスなどから収集される多様な情報を、整合性よく一箇所にまとめ、利用可能な形式に変換するためのデータ基盤は不可欠です。高品質で信頼性のあるデータの上にこそ、BIツールの優れた可視化機能と、生成AIの高度な言語化機能が生きてきます。
さいごに
生成AIがもたらす新しい価値をBIツールと戦略的に連携させることで、企業のデータ活用は単なる過去の可視化から、未来を予測し、新たな価値を創造するフェーズへと進化していきます。
BIツールは、定型レポートや日々の状況把握、KPI管理といった可視化作業において生産性と精度を高め、組織内でのデータ共有や意思決定を円滑にするための不可欠な基盤です。一方、生成AIは、従来の定型的な分析にとどまらず、横断的なデータの探索・分析、未知のトレンドやインサイトの発見を引き出す役割を担います。この二つのツールを、それぞれの得意分野に合わせて上手に使い分け、そして戦略的に組み合わせることで、企業は従来の分析手法だけでは決して得られなかったような、深く、そして多角的なインサイトを発見することができるようになるでしょう。
執筆者プロフィール

山本 進之介
- ・所 属:データインテグレーションコンサルティング部 Data & AI エバンジェリスト
- 入社後、データエンジニアとして大手製造業のお客様を中心にデータ基盤の設計・開発に従事。その後、データ連携の標準化や生成AI環境の導入に関する事業企画に携わる。2023年4月からはプリセールスとして、データ基盤に関わる提案およびサービス企画を行いながら、セミナーでの講演など、「データ×生成AI」領域のエバンジェリストとして活動。趣味は離島旅行と露天風呂巡り。
- (所属は掲載時のものです)
おすすめコンテンツ
データ活用コラム 一覧
- データ連携にiPaaSをオススメする理由|iPaaSを徹底解説
- システム連携とは?自社に最適な連携方法の選び方をご紹介
- 自治体DXにおけるデータ連携の重要性と推進方法
- 生成 AI が切り開く「データの民主化」 全社員のデータ活用を阻む「2つの壁」の突破法
- RAG(検索拡張生成)とは?| 生成AIの新しいアプローチを解説
- Snowflakeで実現するデータ基盤構築のステップアップガイド
- SAP 2027年問題とは? SAP S/4HANAへの移行策と注意点を徹底解説
- Salesforceと外部システムを連携するには?連携方法とその特徴を解説
- DX推進の重要ポイント! データインテグレーションの価値
- データクレンジングとは何か?|ビジネス上の意味と必要性・重要性を解説
- データレイクハウスとは?データウェアハウスやデータレイクとの違い
- データ基盤とは?社内外のデータを統合し活用を牽引
- データ連携を成功させるには標準化が鍵
- VMware問題とは?問題解決のアプローチ方法も解説
- kintone活用をより加速するデータ連携とは
- MotionBoardの可能性を最大限に引き出すデータ連携方法とは?
- データクレンジングの進め方 | 具体的な進め方や注意点を解説
- データ活用を支えるデータ基盤の重要性 データパイプライン選定の9つの基準
- 生成AIを企業活動の実態に適合させていくには
- Boxとのシステム連携を成功させるためのベストプラクティス ~APIとiPaaSの併用で効率化と柔軟性を両立~
- RAGに求められるデータ基盤の要件とは
- HULFTで実現するレガシーシステムとSaaS連携
- データ分析とは?初心者向けに基本から活用法までわかりやすく解説
- 今すぐ取り組むべき経理業務の効率化とは?~売上データ分析による迅速な経営判断を実現するデータ連携とは~
- Amazon S3データ連携のすべて – メリットと活用法
- ITとOTの融合で実現する製造業の競争力強化 – 散在する情報を統合せよ!
- データ分析手法28選!|ビジネスに活きるデータ分析手法を網羅的に解説
- Amazon Auroraを活用した最適なデータ連携戦略
- 生成AIで実現するデータ分析の民主化
- データ活用とは?ビジネス価値を高める基礎知識
- iPaaSで進化!マルチRAGで社内データ価値を最大化
- Microsoft Entra ID連携を徹底解説
- iPaaSで実現するRAGのデータガバナンス
- 銀行DXを加速!顧客データとオープンデータで描く金融データ活用の未来
- データ統合とは?目的・メリット・実践方法を徹底解説
- 貴社は大丈夫?データ活用がうまくいかない理由TOP 5
- 連携事例あり|クラウド会計で実現する経理業務の自動化徹底解説!
- 顧客データを統合してインサイトを導く手法とは
- SX時代におけるサステナビリティ経営と非財務データ活用の重要性
- メタデータとは?基礎から最新動向までFAQ形式で解説
- データは分散管理の時代?データメッシュを実現する次世代データ基盤とは
- API連携で業務を加速!電子契約を使いこなす方法とは
- BIツール vs. 生成AI?両立して実現するAI時代のデータ活用とは
- 脱PoC!RAGの本番運用を支える「データパイプライン」とは
- モダンデータスタックとは?全体像と構成要素から学ぶ最新データ基盤
- データ分析の結果をわかりやすく可視化!〜 ダッシュボードの基本と活用徹底ガイド 〜
- Boxをもっと便利に!メタデータで始めるファイル管理効率化
- メタデータで精度向上!生成AI時代に必要なメタデータと整備手法を解説
- HULFTユーザーに朗報!基幹システムとSalesforceを最短1時間でつなぐ方法
- 脱炭素経営に向けて!データ連携基盤でGHG排出量をクイックに可視化
- データが拓く未来のウェルスマネジメント
- iPaaSが必要な理由とは?クラウド時代に求められる統合プラットフォーム
- 顧客データがつながると、ビジネスは変わる。HubSpot連携で始める統合データ活用
- AI時代のデータ探索:ベクトル検索の手法とデータ連携方法を解説
- RAGのドキュメント検索の精度を高めるチャンク分割とは
- 名刺管理データを真価に変える:CRM・SFA活用で営業力を最大化
- ETL・ELT・EAIの違いとは?データ連携基盤を最適化するポイントを徹底解説
- Marketoと外部ツールのデータ連携で実現するBtoBマーケティングの効率化
- 鍵はデータの構造化!生成AIの回答精度を高める前処理の実践
- データ連携基盤で実現するこれからの防災DX《前編》
- データ連携基盤で実現するこれからの防災DX《後編》
- 効率性と柔軟性を併せ持つ「ローコード×データ連携」で競争優位性を手に入れる!
- Oktaを軸に広がるIdP連携・データストア接続・iPaaS活用の完全解説
- 銀行の不正検知を強化する行内データ活用戦略:予測・予防型への転換ポイント
- 生成AIの費用対効果をどう測る?ROI指標と見落としがちな観点を解説
- AIの嘘をどこまで許容する?情シスが知るべきRAGハルシネーション抑止策
- API連携とは?基本の仕組み・メリット・導入手順などを徹底解説!