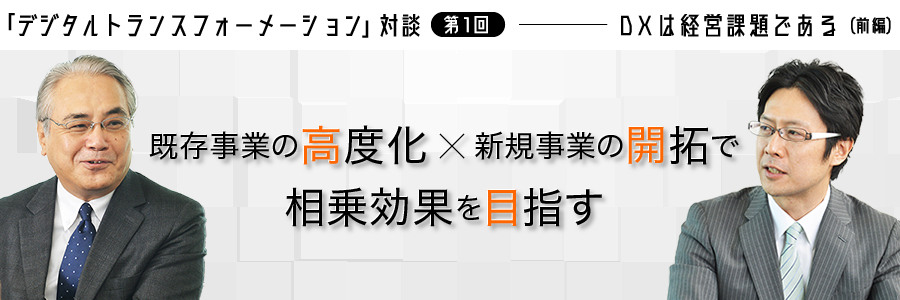昨今、注目を集める「デジタルトランスフォーメーション(DX)」。グローバルでの競争激化、ビジネスの加速、AIやIoTの実用化などを背景に今、本格的に取り組みを進めようとする企業が増えています。しかし、目先の新技術にとらわれた結果、失敗するケースも少なくないようです。経営の観点から考えた際に、本来のDXはどうあるべきなのか、ITR 会長/エグゼクティブ・アナリスト 内山 悟志氏と、セゾン情報システムズ 技術顧問 小野和俊の2人が語りました。
DXを進めるための4つのステップ
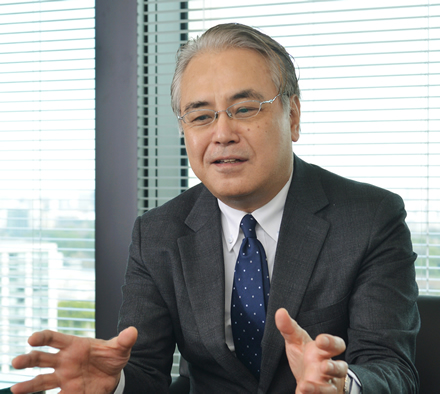
内山
DXに対する意識や取り組みはこれまで業界間でかなり温度差がありましたが、この1年から1年半ほどの間で幅広い業種の経営者まで広がってきたと感じます。Fintechの波がきた金融や、モビリティ社会に向けて動き始めている自動車業界など比較的早くから変革意識があった業界だけでなく、最近ではB to Bの製造業などでも関心が高まっています。DXに関するお客様からの相談は増えていますが、なかでも「DXを推進する組織を作ったけれど、何から始めればよいか分からない」といった相談も多いですね。
DXを進めるには「why、where、what、how」の4ステップがあります。なぜしなければならないのか(why)というファーストステージの企業もありますが、「why」は分かったけれど、どこを目指すべきなのか(where)が分からないという企業が多い印象です。その次になると、具体的になにをすればいいのか(what)、最後に具体的に現状のシステムや制度、人をどうするのか(how)という問題が出てくるんですね。
ですが、このステップを順に踏まない企業も少なくありません。「いきなりPoCをやりたい!AIを使いたい!」と言われても、段階を踏まなければ必ず元に戻ることになるので、一段ずつしっかり上りましょうと話しています。
小野
まさにその通りだと思って聞いていました。技術者の立場で話しますと、心理学用語で「ハンマーと釘」という話があります。なにかというと、たとえばAIやブロックチェーンなど新しい技術が出てきてある程度習得できると、要するに手にハンマーを持った状態になり、なんでも釘に見えて打ちたくなってしまう、ということです。技術は「コレもアレもできるんじゃないか」というワクワク感とセットで手に入れる部分があり、それはいいことなのですが、ともすると「あれもAIでやりましょう」「これもブロックチェーンでやりましょう」となりがちです。すると、あまり必要性がないところで無理やり使うことになってしまいます。
内山
そういったPoCは失敗する確率が高そうですよね。
小野
はい。逆にそこがうまくかみ合うと成功します。たとえば、AIスピーカー「Amazon Echo」には音声認識サービス「Amazon Alexa」が搭載されていますが、昨年このAlexaの開発コンテスト(Amazon Alexaスキルアワード2018)が開催され、セゾン情報システムズがエントリーし、365スキルの中で優勝と特別賞のダブル受賞を果たしました。
ここで受賞した作品が、社内のリフレッシュルームで働く視覚障がいのある方をサポートするものです。リフレッシュルームでは社員にマッサージや鍼を施術していて、これまで次の予約者の呼び出しなどはスタッフ部門がローテーションでサポートしていたのですが、これにより「Alexa、次の人を呼んで」と言うだけで、クラウドの予約台帳を見に行って、予約した人にSlackやSkypeで通知してくれます。予約の繰り上げや、備品の発注までこの仕組みで完結できるようになり、障がいをもつ社員が自立的かつ主体的に働くことができる環境の提供が可能となりました。今後は、リフレッシュルームの空調調整も予定しています。小さな例ではありますが、なぜこの技術を使うのか、なんのためにやろうとしているのかがうまくかみ合って成功したケースだと思います。
内山
技術者がハンマーを使いたがるという話は経営者にも通じるところがあります。「AIがすごい」と聞いて、自社の業務に採り入れようと言い出した結果、現場が踊らされてしまう。ただ、それではうまくいかないという理解が進んできたのがこの1年だったように感じます。
DXは2種類に分類できる
内山
DXとひとことで言っても、質が違うものが2種類含まれます。1つは、既存事業を高度化するためにデジタル技術をうまく使おうというもの。たとえば製造業の現場や、建設の工事現場などにおけるIoTやAIの活用もこれに当たります。もう1つが、まったく新しいビジネスを創出するもの。どちらも同じように「DX」と呼ばれています。

どちらもビジネスを変革するという目的は似ていますが、手法やアプローチはかなり違うので、どちらに軸足を置いて進めるのかを決めてからスタートする必要があります。往々にして、社長は新規事業と言っていて、事業部長は既存事業の高度化と言っている……というようなことが起こりやすいので、まずは方向性を明確にするところから始めたほうがいいでしょう。
今はちょうどDXのための組織立ち上げや中期経営計画策定などが進んでいますが、どうしても従来のようにPDCAを回そうという意識が強いです。DXの場合、多少リスクをとってでも新しいことに挑戦するといった、ベンチャーのようないわゆるデジタルネイティブのカルチャーで臨んだ方がいいのに、お行儀が良すぎて踏み込めていない企業が多いのかなと思います。
小野
そもそもベンチャー企業はあまりDXとは言いませんよね。最初からデジタルですから。デジタルじゃない会社がデジタルになることが、“トランスフォーメーション”になるんです。その意味では、いわゆる大手企業においてどうDXを進めるのかが一番の課題になっています。
先ほど、DXには2種類あることを紹介いただきましたが、新規事業を立ち上げるとしても既存の強みを活かせない事業になるならば、その領域では正直ベンチャーの方が強いと思います。これまで持っていた信用やお客様の基盤、過去のデータといった既存資産とつなげてこそ大企業が取り組む意義があるのではないでしょうか。
内山
2000年に『イノベーションのジレンマ』が出版され大変注目を集めましたが、今年の2月に『両利きの経営』という本が出ました。まさに、今おっしゃったような、大企業がDXをやる際にはその強みとなる従来型事業を活かし、それを成功させる「深化」と新しい世界にチャレンジする「探索」をいかに両立させるかという話が書かれています。日本の大企業に対する直接的なメッセージとして、届きやすい考えがようやく出てきたと思いました。
2つのモードを「バイモーダル」でつなぐ

小野
HULFTでも昨年から「バイモーダル」というメッセージを全面的に出していますが、文化的な融合は半年や1年ではできないと思うんです。安定性重視でSoR的な「モード1」と、速度重視でSoE的な「モード2」のどちらにもそれぞれの良さがあります。先ほども話したように大企業のDXでは既存のアセット、既存のデータをつながなければ意味がないと思いますが、そのときに「あなたたちのやり方はモード1だから、変わってください」とみんなに強いるのは現実的ではないですし、望ましくもないでしょう。モード1の安定性はすごくかけがえのないものですし、1回の失敗で大事故になってしまうような事業はモード1としてやり続けなければなりません。特に既存企業の持つデータセットは個人情報などが含まれることも多く、それに関してはモード1としてしっかり守っていただけるようお願いしたいところです。もちろんこれらのデータもDXでうまれた新規事業とつなげる必要がありますが、無理やり融合すると破綻してしまいます。それぞれ個別にあって、お互いをリスペクトしながら、つなげるところさえできればいいのではないか。そして、両者をつなぐ現実解のひとつがHULFTであるというメッセージを出しています。
内山
モード1とモード2があるとどうしても優劣や善悪で測りがちですが、お互いの良さがありますし、おそらくDXで取り組んだ新規事業もいずれモード1になっていくんです。いつまでもトライ&エラーではなく、あるステージからは安定性や拡張性が必要になることが出てきます。これからは両者の得意領域を教えあい、共有しあって共存するような企業経営になっていくべきです。
小野
HULFTも、もともとはメインフレームとUNIXの連携ソフトというイメージが強かったのですが、世に出た当初は先進的なモード2的なものだったのではと思います。
内山
その頃のことをよく覚えていますが、当時、オープンシステムは非常に不安定で、重要なシステムは乗せられないと思われていました。それをどんどん使っていくために、旧来のきっちりとしたメインフレームとつなげなければいけないというニーズに対してHULFTが出てきたんです。
今、HULFTでは「ReBORN~創造と挑戦~」というメッセージを打ち出していますが、ちょうど当時と同じ現象が起きているように思います。WindowsもUNIXもLinuxも含まれる「従来のシステム」と、たとえばクラウドやIoTのようなエッジコンピューティング、さらに新しい技術をつなぐところに新しいチャンスが生まれています。

小野
HULFTはどの時代でも文化的なギャップを含め、技術の新旧をつなぐ架け橋のような存在であり続けたのではと思います。また何年か経てば、クラウドもモード1になってしまうかもしれません。
DXやデジタルディスラプションといったことが言われますが、「今、何と何をつなぐ必要があるのか」を考えなければならない時代に、HULFTの「ReBORN~創造と挑戦~」というメッセージはふさわしいタイミングだったのかもしれません。