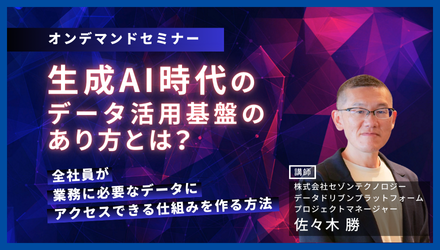モダンデータスタックとは?全体像と構成要素から学ぶ最新データ基盤
近年、データ活用による業務効率化や新たな価値創出に取り組む企業が増えています。その際に重要となるのが、時代に合った柔軟なデータ基盤の構築です。そこで注目されているのが、クラウドを前提に複数のツールを組み合わせる 「モダンデータスタック」 というアプローチです。
モダンデータスタックは、従来よりも容易にデータを収集・分析できる環境が整えられ、非構造化データやリアルタイム処理にも対応可能です。その結果、専門部署だけでなく事業部門の担当者もデータに基づいた意思決定を行いやすくなります。
本記事では、モダンデータスタックの定義・特徴から具体的な構成要素、導入メリット、収集戦略までを整理します。
![]() Seiji Hosomi
- 読み終わるまで 7分
Seiji Hosomi
- 読み終わるまで 7分
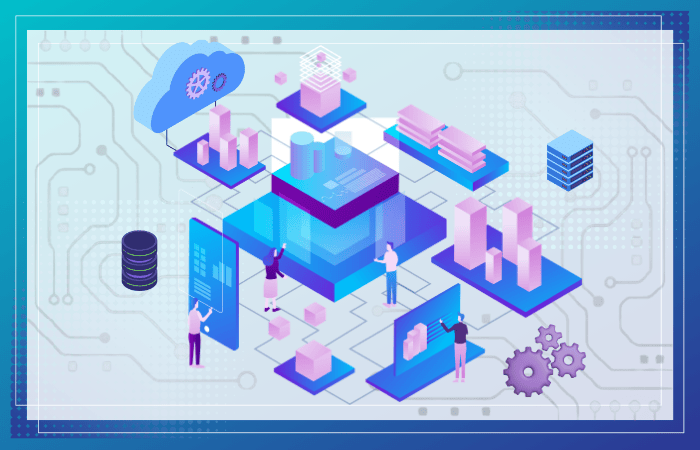
モダンデータスタックとは何か
モダンデータスタックとは、クラウド上で構築される柔軟なデータ基盤を指します。従来のオンプレ環境ではサーバー管理や拡張に大きな負担がありましたが、クラウドの利用によってリソースを柔軟に確保できるようになりました。
特徴的なのは、単一の巨大システムではなく、機能に特化したSaaSツールを組み合わせる点です。データウェアハウス、ETL/ELT、リアルタイム収集基盤、BIツールなどを必要に応じて選択し、最新の環境を短期間で整えられます。これにより大規模データの取り扱いが簡単になり、高度な可視化やAIを用いた高度分析も実現しやすくなります。
モダンデータスタックの特徴とメリット
モダンデータスタックの大きな特徴は、クラウドネイティブなツールを組み合わせることで以下のようなメリットを得られることです。
- 柔軟性と拡張性:機能が明確に分離されているため、新しいツールの導入や入れ替えが容易で、技術革新にも素早く対応できる
- コスト効率:コンピューティングリソースを必要なときに必要な量だけ使用することでコストを抑えられる
- リアルタイム性:リアルタイム処理が可能なツールを導入することで、即時性を求める分析ニーズにも応えやすい
- グローバル対応:クラウドベースであるため、各国の拠点からデータを収集する際の制限が少なく、グローバルなデータ活用にも向いている
従来のデータ基盤との違い
従来のオンプレミス型のデータ基盤では、ハードウェアやソフトウェアの購入、メンテナンスなどに大きな初期投資が必要で、スケールアウトが難しく、非構造化データや大容量データへの対応に時間や費用がかかりやすかったのも課題です。
一方、モダンデータスタックではクラウド上で稼働するサービスをメインに利用するため、データ容量が増加しても柔軟に対応できます。サーバーのダウンやメンテナンス負荷が軽減されるほか、ツール間の連携が容易であり、短期間で最新の分析環境を構築できます。
必要なツールを都度最適に選び連携するため特定ベンダーへの依存度も低く、要件にあわせて最適なサービスを導入しやすい点も従来基盤との大きな違いです。
モダンデータスタックが注目される背景
近年、あらゆるオンラインサービスから得られるデータは爆発的に増加し、企業はそれらを素早く分析する必要に迫られています。従来型のシステムでは拡張に限界があり、リアルタイム性の高い分析や新しいテクノロジーとの統合が容易ではありませんでした。
こうした状況のなかで、クラウドを前提としたモダンデータスタックは、拡張性と導入スピードの両立が可能な手段として注目を浴びています。さらに、少人数でも運用管理がしやすい点や専門知識がなくてもツールを使いこなしやすい点も大きな魅力になっています。
その結果、スタートアップから大企業までモダンデータスタックを取り入れる動きが広がり、データドリブン経営を支える基盤として定着しつつあります。
モダンデータスタックを支える主要構成要素
モダンデータスタックは、いくつかの機能を分担するツール群で構成されます。まずは収集したデータを保存し、分析に耐えうる形に加工。最後にBIツールなどで可視化・活用する流れが一般的です。
現場で扱うデータや分析の規模、取り込む頻度によって最適なツール構成は変わります。しかし基本的には、データ収集・取り込み、ストレージ、加工、分析・可視化、そしてモニタリングと品質管理という段階のツールを組み合わせることで強固なデータパイプラインを構築できます。
データ収集・取り込み
多様なデータソースから情報を取得し、データウェアハウスやデータレイクへ転送するフェーズです。ログデータやイベントデータをリアルタイムで取り込めるツールを用いると、顧客行動の即時分析につながります。
BI活用においては品質やタイミングが重要であり、適切なパイプラインが整備されれば社内でのデータ利用がスムーズに進みます。最初にこの段階で整合性が崩れると後工程へ影響を及ぼすため、信頼性の高い取り込み基盤を選定するべきです。
例えば HULFT Square はクラウド型のデータ連携プラットフォームとして幅広いSaaSを統合でき、DataSpider のようなミドルウェアはオンプレミス環境との連携に適しています。
-
▼データレイクについてもっと詳しく知りたい
⇒ データレイク|用語集
データストレージ
集めたデータを大量かつ安全に保管する領域で、クラウド上のデータウェアハウスやデータレイクが一般的です。これらは拡張性が高く、数テラバイトからペタバイト規模のデータも対応可能です。
ストレージの選択肢としては、SnowflakeやBigQuery、Redshiftなどが代表的です。特にインフラ管理を大きく削減できる点が魅力で、企業の状況に合わせて必要な計算リソースをオンデマンドで利用できます。
スケーラビリティとコスト最適化を両立するストレージ環境を整備することで、今後のデータ増加に効率的に対応し、組織全体でデータを共有しやすくなります。
データ変換・加工
ETL/ELTツールを使って、生のデータを分析しやすい形へ変換するステップです。近年はETLではなく、ストレージに取り込んだ後にTransformationを行うELT方式を採用するケースが増えています。
例えば、ログデータやイベント情報などの非構造化データをテーブル形式に整理したり、重複を除去して整合性を保ちやすい状態にすることが目的です。加工の質が分析精度に直結するため、設計段階でビジネス要件を十分に洗い出すことが求められます。
コードを書くスキルがなくても利用できるデータパイプライン管理ツールもあり、専門家と担当者が協力して運用することで効率的なデータ整備が実現します。
データ分析・可視化
BIツールなどを用いて、ビジネスインパクトのある情報を抽出し、視覚的に表現するフェーズです。グラフやダッシュボードの作成により、担当者や経営層が直感的にデータを把握できるようになります。
分析対象の拡大や短期的な施策検討が求められる企業にとっては、リアルタイムの可視化が意思決定スピードを高めるカギとなります。
データサイエンスの観点では、AIや機械学習のモデル化にも応用が可能です。さらに近年では、生成AIを業務活用するための基盤としても注目されています。例えば HULFT Square は、RAG(Retrieval-Augmented Generation)の構築に必要なデータを既存システムやSaaSから取り込み、AIが利用しやすい形に変換する橋渡しの役割を果たします。
データモニタリングとオブザーバビリティ
データパイプラインが正しく稼働しているか、またデータ品質が保たれているかを監視する仕組みです。ここで問題を早期発見できることで、システム障害やデータ欠損によるビジネス影響を最小限に抑えられます。
さらに、同じように見えるデータの挙動を追跡し、異常を検知することはデータセキュリティやコンプライアンス順守の観点からも重要です。
組織全体のデータ活用を円滑に進めるには、日常的なモニタリングと迅速なトラブルシューティングを可能にする仕組みが欠かせません。
この領域では HULFT DataCatalog のようなメタデータ管理ツールが、データの所在や定義を明確化する役割を果たします。
モダンデータスタックにおけるデータ収集のポイント
データを収集する際に押さえておきたいポイントですが、モダンデータスタックの特徴として、あらゆるデータソースからの情報を取り込みやすい点があります。しかし、何も考えずに全てのデータを収集すると、運用や分析工程で無駄が生じることもあるため、まず収集要件を明確にすることが重要です。
収集方法をリアルタイムかバッチかで選択する場面もあり、外部からのデータを取り扱う際はセキュリティ上のリスクと法的な遵守事項を踏まえたルール作りも大切です。
これらを総合的に整理して優先度を付けることで、モダンデータスタックによるデータ収集をスムーズに進め、企業が抱えるビジネス課題に合わせたデータ基盤を築くことができます。
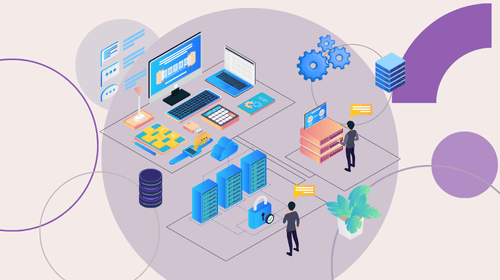
収集要件の明確化と優先度設定
データ収集を開始する前に、ビジネス目標に直結する必要な指標を洗い出し、収集対象を明確にすることが重要です。すべてのデータを拾うのではなく、最終的に活用するデータにフォーカスすることで無駄を省けます。
優先度を設定する際は、時間コストや技術リソース、データの品質確保を考慮してください。重要度の高いデータから扱うことで、導入後の成果を早期に見込みやすくなります。
そのためには部門間のコミュニケーションも不可欠です。収集すべき項目や取扱い方針を共有しながら、最適な範囲とスケジュールで進めると効果的です。
リアルタイムデータとバッチデータの使い分け
リアルタイムでのデータ収集は、ユーザー行動を即座に反映した分析やアラート発行に有効です。一方、バッチ処理の場合は大量のデータをまとめて定期的に処理できるため、システム負荷を抑えつつ確実な集計が可能です。
どちらを選ぶかは分析の目的によって異なります。リアルタイム分析が必要な場合はストリーミングツールの活用、日次や週次レポートを主にする場合はバッチ処理が向いています。
意思決定のスピードと精度を両立させるため、目的ごとに適したパイプラインを設定しましょう。
セキュリティとガバナンスへの配慮
データ収集時には、取り扱う情報の機密度やプライバシーリスクを考慮し、厳格なセキュリティ対策と権限管理を行う必要があります。取り扱いが甘いと個人情報保護の観点から違反を招く恐れもあります。
ガバナンスを強化するには、アクセスログを残すことや暗号化を実施することなど、運用ルールの整備が欠かせません。法律や業界標準に準拠した手法を徹底して取り入れることで、組織全体の信頼性を高められます。
また、データ品質やデータ定義の統一もガバナンスの一部です。収集されたデータが使いものにならなければ、後工程で大幅な修正が必要となるため、最初の段階からデータ管理体制をしっかりと整備しましょう。
モダンデータスタック導入によるビジネスメリット
モダンデータスタックの導入は、多角的な観点から企業に利益をもたらします。特にデータ利活用のスピードアップとコスト削減、新たなビジネスモデルの創出やイノベーション推進においては顕著な効果があります。
また、データを組織全体で共有できることで、各部門が共通の指標をもとに動けるようになります。これにより、部門間の連携がスムーズになるだけでなく、社内知識を結集した高度な戦略判断が可能となります。
結果として、市場ニーズへの素早い対応や顧客満足度の向上が期待できます。ここでは代表的なメリットについて詳しく見ていきましょう。
スケーラビリティの向上
クラウドベースのモダンデータスタックは、データ量やアクセス数の急増に対して自動的にリソースを拡張できます。これにより、一時的な負荷増にも安定して対応でき、ユーザー体験やビジネスチャンスを逃しにくくなります。
大規模なデータ分析を必要とするAIや機械学習プロジェクトにも迅速にアクセスできるため、新たなビジネス価値の創出につなげやすい環境を構築できます。
コスト効率の改善
オンプレミス環境ではサーバー規模に応じた膨大な初期投資が求められましたが、モダンデータスタックはクラウドの使用量ベース課金で開始できるため、大きなキャッシュアウトを避けながら必要な機能を揃えられます。
その結果、導入のハードルが下がり、小規模なチームでもデータ活用に踏み切ることが可能になります。全体として大幅な省コスト効果が得られ、ビジネスの成長に投資を回せるのは大きなメリットです。
データの民主化と組織力強化
モダンデータスタックは、専門知識がなくても扱いやすいツールを組み合わせて統合することで、データを組織内の広範囲に開放できます。これにより、現場から経営層までが共通の指標をリアルタイムで共有し、意思決定に役立てられます。
また、チームメンバー同士がデータを見ながら議論し、最適な施策を検討する土壌を育むことができます。結果として、企業文化としてのデータドリブンマインドが浸透し、より適切な意思決定が繰り返し行われるようになります。その効果は、売上増加やコスト削減以上の価値となって現れます。
意思決定の迅速化
リアルタイムで取得されるデータや、更新頻度の高いダッシュボードは、経営者や事業担当者が瞬時に状況を把握し、次の一手を素早く打つための材料になります。
意思決定の迅速化は、顧客満足度の向上や新規プロジェクトのスピーディな立ち上げにも直結するため、企業全体の成長エンジンとなります。
まとめ
モダンデータスタックは、クラウドを活用した柔軟かつ拡張性の高いデータ基盤であり、アジリティを持ってデータを活用するための要となります。これによりスケールアップやコストの最適化がしやすく、素早く実証しやすい環境が整います。
導入時には、データ収集の優先順位やリアルタイム処理の必要性、セキュリティの確保などの検討が不可欠です。運用体制や予算を踏まえ、どの機能を優先的に活用するかを明確にすることが成功のカギとなります。
今後さらにデータの活用価値が高まるなか、モダンデータスタックはより広範な領域で導入が進むことが予想されます。自社の状況に合わせて最適な構成を選び、データドリブンを実現するために役立ててください。
参考情報
本記事で触れた製品の詳細は以下をご参照ください。
- HULFT Square|クラウド型データ連携プラットフォーム
クラウドやSaaSを中心に、多様なデータソースを簡単に統合可能 - DataSpider|データ連携ミドルウェア
オンプレミス環境を含め、複雑なシステム連携を柔軟に実現 - HULFT DataCatalog|メタデータ管理ツール
データ資産を横断的に把握し、ガバナンスや品質管理を支援
執筆者プロフィール

細見 せいじ
- ・所 属:マーケティング部
- 都内のSierで約10年システム開発に従事したのち、2016年 アプレッソ(現:セゾンテクノロジー)にjoin。 データ連携ソフトウェアDataSpiderの開発エンジニア→プロジェクトマネージャーを経て、現在はマーケティング部でデータ利活用領域を担当。 システムエンジニア時代に培った IT システム活用経験をベースに、お客様の『データ利活用』『デジタル・トランスフォーメーション』を支援している。
- (所属は掲載時のものです)
おすすめコンテンツ

データ連携にiPaaSをオススメする理由|iPaaSを徹底解説
iPaaSがなぜデータ連携に適しているのか、従来の方法とどのように異なるのか、そして実際にどのように活用されているのかを徹底解説します。
データ活用コラム 一覧
- データ連携にiPaaSをオススメする理由|iPaaSを徹底解説
- システム連携とは?自社に最適な連携方法の選び方をご紹介
- 自治体DXにおけるデータ連携の重要性と推進方法
- 生成 AI が切り開く「データの民主化」 全社員のデータ活用を阻む「2つの壁」の突破法
- RAG(検索拡張生成)とは?| 生成AIの新しいアプローチを解説
- Snowflakeで実現するデータ基盤構築のステップアップガイド
- SAP 2027年問題とは? SAP S/4HANAへの移行策と注意点を徹底解説
- Salesforceと外部システムを連携するには?連携方法とその特徴を解説
- DX推進の重要ポイント! データインテグレーションの価値
- データクレンジングとは何か?|ビジネス上の意味と必要性・重要性を解説
- データレイクハウスとは?データウェアハウスやデータレイクとの違い
- データ基盤とは?社内外のデータを統合し活用を牽引
- データ連携を成功させるには標準化が鍵
- VMware問題とは?問題解決のアプローチ方法も解説
- kintone活用をより加速するデータ連携とは
- MotionBoardの可能性を最大限に引き出すデータ連携方法とは?
- データクレンジングの進め方 | 具体的な進め方や注意点を解説
- データ活用を支えるデータ基盤の重要性 データパイプライン選定の9つの基準
- 生成AIを企業活動の実態に適合させていくには
- Boxとのシステム連携を成功させるためのベストプラクティス ~APIとiPaaSの併用で効率化と柔軟性を両立~
- RAGに求められるデータ基盤の要件とは
- HULFTで実現するレガシーシステムとSaaS連携
- データ分析とは?初心者向けに基本から活用法までわかりやすく解説
- 今すぐ取り組むべき経理業務の効率化とは?~売上データ分析による迅速な経営判断を実現するデータ連携とは~
- Amazon S3データ連携のすべて – メリットと活用法
- ITとOTの融合で実現する製造業の競争力強化 – 散在する情報を統合せよ!
- データ分析手法28選!|ビジネスに活きるデータ分析手法を網羅的に解説
- Amazon Auroraを活用した最適なデータ連携戦略
- 生成AIで実現するデータ分析の民主化
- データ活用とは?ビジネス価値を高める基礎知識
- iPaaSで進化!マルチRAGで社内データ価値を最大化
- Microsoft Entra ID連携を徹底解説
- iPaaSで実現するRAGのデータガバナンス
- 銀行DXを加速!顧客データとオープンデータで描く金融データ活用の未来
- データ統合とは?目的・メリット・実践方法を徹底解説
- 貴社は大丈夫?データ活用がうまくいかない理由TOP 5
- 連携事例あり|クラウド会計で実現する経理業務の自動化徹底解説!
- 顧客データを統合してインサイトを導く手法とは
- SX時代におけるサステナビリティ経営と非財務データ活用の重要性
- メタデータとは?基礎から最新動向までFAQ形式で解説
- データは分散管理の時代?データメッシュを実現する次世代データ基盤とは
- API連携で業務を加速!電子契約を使いこなす方法とは
- BIツール vs. 生成AI?両立して実現するAI時代のデータ活用とは
- 脱PoC!RAGの本番運用を支える「データパイプライン」とは
- モダンデータスタックとは?全体像と構成要素から学ぶ最新データ基盤
- データ分析の結果をわかりやすく可視化!〜 ダッシュボードの基本と活用徹底ガイド 〜
- Boxをもっと便利に!メタデータで始めるファイル管理効率化
- メタデータで精度向上!生成AI時代に必要なメタデータと整備手法を解説
- HULFTユーザーに朗報!基幹システムとSalesforceを最短1時間でつなぐ方法
- 脱炭素経営に向けて!データ連携基盤でGHG排出量をクイックに可視化
- データが拓く未来のウェルスマネジメント
- iPaaSが必要な理由とは?クラウド時代に求められる統合プラットフォーム
- 顧客データがつながると、ビジネスは変わる。HubSpot連携で始める統合データ活用
- AI時代のデータ探索:ベクトル検索の手法とデータ連携方法を解説
- RAGのドキュメント検索の精度を高めるチャンク分割とは
- 名刺管理データを真価に変える:CRM・SFA活用で営業力を最大化
- ETL・ELT・EAIの違いとは?データ連携基盤を最適化するポイントを徹底解説
- Marketoと外部ツールのデータ連携で実現するBtoBマーケティングの効率化
- 鍵はデータの構造化!生成AIの回答精度を高める前処理の実践
- データ連携基盤で実現するこれからの防災DX《前編》
- データ連携基盤で実現するこれからの防災DX《後編》
- 効率性と柔軟性を併せ持つ「ローコード×データ連携」で競争優位性を手に入れる!
- Oktaを軸に広がるIdP連携・データストア接続・iPaaS活用の完全解説
- 銀行の不正検知を強化する行内データ活用戦略:予測・予防型への転換ポイント
- 生成AIの費用対効果をどう測る?ROI指標と見落としがちな観点を解説
- AIの嘘をどこまで許容する?情シスが知るべきRAGハルシネーション抑止策
- API連携とは?基本の仕組み・メリット・導入手順などを徹底解説!