「HULFT DAYS 2022」 今年も開催しました!(その2)
【第14回】

2022年11月8日から11月10日の三日間にわたり、今年も開催しました「HULFT DAYS 2022」から、開催一日目のオフライン会場の様子をレポートいたします。
全三回でお届けしますレポート記事の二回目です。
NewsPicks Brand Design特別講演
DXブームへの処方箋。競争戦略の視点から見たDX
楠木 建(一橋ビジネススクール教授)

次はちょっと辛口な内容で、流行語の「流行の表面だけ」に飛びつくことにくぎを刺すような講演内容でした。
登壇では「解っていないのに流行語っぽいことを言う人の例」として、「やたらシナジーを連呼する人」が例に出されていました。DXなどの昨今よく聞く言葉でも、似たようなことはあるように思えます。
いつの時代でも「その当時の流行り言葉」があり、同じようなことがなされて来ました。むしろ、そういう状況こそが本質ではないでしょうか。
例えば「○○の登場で仕事がなくなる」ようなことが、これまで何回も言われてきました。オートメーションで仕事がなくなる(1956年)、コンピュータで仕事がなくなる(1965年)、ロボットで仕事がなくなる(1983年)、などなどです。そして今「AIで仕事がなくなる」と言われています。

流行りの本質を考えず、表層だけ真似をして失敗する例も多くあります。例えば「サブスク」、サブスク化の成功例として知られるのは、昔ながらのソフトウェアのパッケージ売りをクラウド経由のサブスクリプションビジネスに変革したAdobe社(Photoshopなどを開発販売する社)での取り組みです。しかしAdobeがサブスクで成功したのは、彼らのビジネスの特性(文脈)が「サブスクに向いている」から、あるいは「そのようになるべく時間をかけた準備」があってこそです。
そういうことを踏まえないで、「料金支払いだけサブスクにする」ような表層的取り組みが昨今流行ったことでした。例えば飲食店でのサブスク、たくさん食べれば元が取れるので赤字になるなどして、サービス中止が相次ぎました。
何がいけないのでしょうか。成功例の文脈(本質)を無視した「飛び道具(流行り言葉)の表層だけ」をコピーペーストしたので失敗しているわけです。流行り言葉が、こういう失敗を生みだしてしまうことがあります。そうならないためには、流行り言葉の本質を見極めて、自社の文脈に位置付けてみて、それできちんと機能するかを考える必要があります。
昨今の流行り言葉である「DX」でも同じように、考えて取り組む必要があります。
その取り組みの本質が、コスト削減としてのデジタル変革(「デジタル代替:DS」と登壇では紹介)であり、旧来のアナログをデジタルに置き換える取り組みであるなら、迷わずに取り組めばよいでしょう。なぜなら、取り組めばコストが下がり、デジタル世界の競争で今後もさらにコストは下がることが期待できるためです。
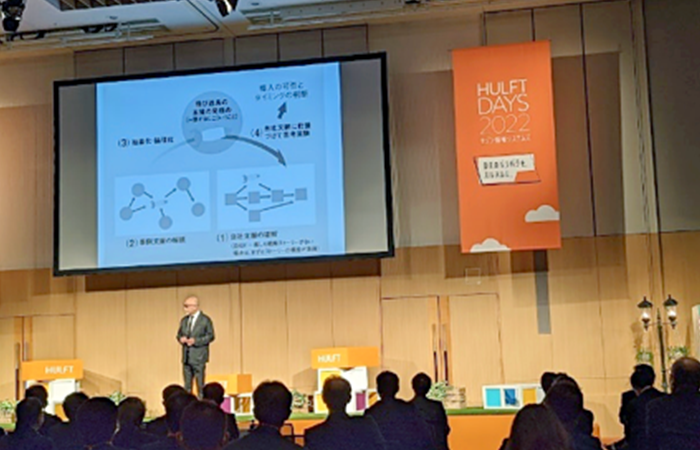
その本質が事業変革の場合は、表層だけを真似するのではなく、自社の文脈を踏まえた上での全体、総体としての「ストーリー」を踏まえてどうするか考える必要があります。その上で取り組むことで、「競争優位を生み出す違い」が生まれるかどうか考える必要があります。
特別講演
改革派CIOに日経BP研究員が迫る、日本企業のDXが進まない真因と処方箋
小野 和俊(株式会社クレディセゾン 取締役 兼 専務執行役員 CTO 兼 CIO)
大和田 尚孝(日経BP総合研究所 イノベーションICTラボ所長)

次に、クレディセゾン社でデジタル変革の実現に取り組まれており、元「DataSpider」の開発者でもある、小野和俊氏に登壇を頂きました。
今回のイベントはDXをテーマで開催させていただきました。デジタル活用は取り組む必要があると言われつつ、多くの日本的企業ではうまく進められていないのではないでしょうか。小野和俊氏はまさに、日本的企業文化でのDX推進に取り組まれているということで登壇を頂きました。
クレディセゾン社は世間でも広く知られた伝統ある会社ですが、以前はデジタル技術の利活用が十分に進んでいませんでした。今ではデジタルを活用した取り組みが進みつつあり、IT自体を導入したのみならず、ITを活用した新商品やサービスの開発が進められるようになり、住宅ローンの「フラット30」では売り上げが倍になるなど成果も上がっているとのことです。
デジタル技術の活用を推し進めるにおいて、取り組み自体がうまく進められずに失敗するだけでなく、そもそも成果が上がらない取り組みをして失敗することがあります。世間でも「PoCはしたものの、その後成果が上がらない」はよくある話です。そこで、「CX(顧客体験の改善)かEX(従業員体験の改善)に貢献する取り組みであるかどうか」を基準として、取り組みをすべきかどうか判断しているとのことでした。
「ITの内製化」にも取り組んでいます。事業会社は外部ベンダに開発を依頼することが多いですが、「スピードが遅く、コストが高い」「要件の硬直性」「ノウハウが残らない」ことから、内製化すべきと考えているとのこと。
業務の現場が自らITを活用できるなら、何か気がついたらすぐにITに反映し、その結果から学びを得て加速度的に先に進むことすらできますが、外注していると何かあるたびに変更の要望を書面にまとめて開発を依頼して……と時間も予算もかかります。
そのような状況では「変更自体がハイコスト」になり、IT利活用も硬直的になります。さらに悪いことに、今やIT活用が企業の勝ち負けを分けるようになったのに、そのITの使いこなし方を外注してしまって「ITに関するノウハウが手の内に残らない」のは重大な問題だと言えます。

しかし内製化で問題になるのは、「必要な人材をどうやって確保するか」です。
世間で多い失敗は、苦労してなんとかIT人材を採用するも、IT人材の価値観(モード2)と、日本的企業の価値観(モード1)が衝突してしまい、短期間で退職してしまう不幸なケースです。
残念ながら、IT人材をモード1文化に合わせてもらおうとすると退職を招いてしまうことが多いのが現実です。
かといって、これからはデジタルの時代だと企業全体をモード2(デジタル)に変えてしまうことは現実的に大変で、長年にわたり事業を支えてきた「貴重なモード1人材」を失うことにもつながります。
そこで小野氏が提案するのは「バイモーダル」の考え方です。考え方や文化の違う「モード1」と「モード2」を、組織として両方とも尊重する取り組みです。考え方の違いにより、衝突や不満なども起こりますが、互いが互いに尊重するよう、双方の価値観に寄り添いつつ反対側の価値も認めるよう促すことで、コンフリクトを調整して協調を促します。
社内での人材育成にも取り組んでいます。ITに詳しい人材をコアデジタル人材として、事業側の旧来の人材から希望者を短期集中でトレーニングしています。このような取り組みにより、ビジネスを深く理解しデジタルも解る「ビジネスデジタル人材」を養成しています。このような人材は、DXの取り組みでは非常に活躍する人材になります。

また、内製化をすれば「伴走型の開発」も可能になります。外注した場合に、システムの開発と利用の間で線を引いて責任範囲を明確にすることが、どうしても行われてしまいます。しかし、業務側が何を作るか決めてIT側はそれを作るような分担関係より、エンジニアが業務側と一緒になって何を作るべきかをも含めて開発した方が、開発の速度も柔軟性も高くなります。そこで、エンジニアと事業側を融合した開発「伴走型の内製開発」に取り組んでいます。
また、旧来のIT活用は「従来の業務をIT化により効率化する」取り組みが多かったものの、インターネットやスマートフォンが日常で広く使われるデジタル時代になってからは状況が変わっているとしています。
例えば、Uber Eatsで食べ物を頼むと、自分の注文を持ってきている自転車が今どこを走っているのかリアルタイムで見ることができます。食べ物が届くかどうかの観点では必須の機能ではないものの、自転車が道を間違えて通り過ぎてしまうのをスマートフォンで見ているような体験すら、それ自体が何か面白さがあり、有用な顧客の利用体験(CX)であることがあります。
旧来的なIT利活用の目線では、このような利用体験が見落とされることがあります。今後は、デジタル化によって生まれる新しい状況を踏まえた、新しい常識での新しい体験の提供にも取り組むことが必要になります。
HULFTイベントレポート 一覧
- 第1回 スマート工場EXPOに出展しました!
- 第2回 関西IoT/M2M展に出展しました!
- 第3回 Japan IT Week 春「AI・業務自動化展」に出展しました!
- 第4回 スマートファクトリーJapan 2019 に出展しました!
- 第5回 TerraSkyDay 2019にDataSpider Cloudを出展しました!
- 第6回 第13回 ITヘルスケア学会 学術大会に出展しました!
- 第7回 Box World Tour Tokyo 2019
- 第8回 シーコン・フォーラム2019でDataSpiderとPIMSYNCを紹介しました!
- 第9回 FIT2019(金融国際情報技術展)に出展しました!
- 第10回 HULFT DAYS 2019 今年も開催しました!(その1)
- 第10回 HULFT DAYS 2019 今年も開催しました!(その2)
- 第10回 HULFT DAYS 2019 今年も開催しました!(その3)
- 第11回 「RPA DIGITAL WORLD 2019」に出展しました!
- 第12回 「地方創生 EXPO」に出展しました!
- 第13回 HULFT DAYS 2021 今年も開催しました!
- 第14回 HULFT DAYS 2022 今年も開催しました!(その1)
- 第14回 HULFT DAYS 2022 今年も開催しました!(その2)
- 第14回 HULFT DAYS 2022 今年も開催しました!(その3)
- 第15回 DXをもっと加速!HULFT DAYS STEP UP Seminar 2022 を開催しました!
- 第16回 HULFT Technology Days 2023 今年も開催しました!(その1)
- 第16回 HULFT Technology Days 2023 今年も開催しました!(その2)
- 第16回 HULFT Technology Days 2023 今年も開催しました!(その3)
- 第17回 HULFT Technology Days 2023 今年も開催しました!(Business Day:その1)
- 第17回 HULFT Technology Days 2023 今年も開催しました!(Business Day:その2)
- 第18回 HULFT Technology Days 2023 今年も開催しました!(Technical Day:その1)
- 第18回 HULFT Technology Days 2023 今年も開催しました!(Technical Day:その2)
- 第19回 AWS re:Invent 2023出展特設ページ
- 第20回 HULFT Technology Days 2024 今年も開催しました!(1日目:その1)
- 第20回 HULFT Technology Days 2024 今年も開催しました!(1日目:その2)
- 第21回 HULFT Technology Days 2024 今年も開催しました!(2日目)
- 第22回 HULFT Technology Days 2024 今年も開催しました!(3日目)


