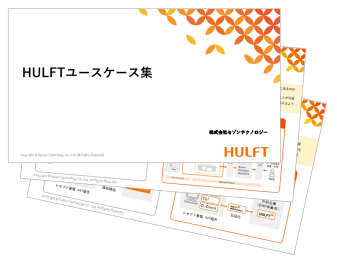ファイル転送・超入門
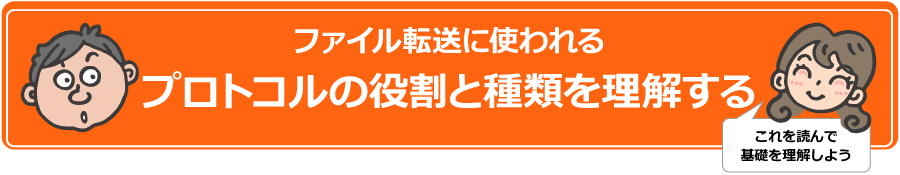
安全でスピーディーなファイル転送を実現するために
プロトコルを理解しよう!
メールへの添付では送受信できないような大容量データ。このようなデータを社内外でやりとりする際に、ファイル転送サービスを使うことが日常的となっています。また、社内やプライベートでホームページを更新した経験がある方は、ほとんどの場合、ファイル転送ソフトを利用されているはずです。
このように、ファイル転送の詳しい仕組みについて知らなくても、多くの方がファイル転送サービスを使いこなしています。
ファイル転送サービスの裏側では、ふだんあまり気にしたことがない「プロトコル」というものが機能しています。ファイル転送とは切り離せない「プロトコル」の仕組みや役割、その種類についてまとめました。
1. プロトコルとはファイル転送の際に“コンピューターがデータをやりとりする約束”のこと
1-1 ファイル転送になぜプロトコルが必要なのか?~プロトコルの仕組み
ファイル転送サービスを利用して、ファイルを送る場合、そのまま大きなデータを送っているわけではありません。ファイル転送は、データを一定の大きさに分解し、すべて送った後にもう一度組み立て直すというやり方で、大容量のファイルを転送しているのです(この分解したデータのことを“パケット”といいます)。 そのため、パケットをやりとりする方法と、受け取ったパケットを元のデータに組み立てるための方法を、事前に決めておく必要があります。この約束事を「プロトコル」と呼んでいます。
1-2 ファイル転送時、大容量データは分割して送受信される
少し具体的な例を出してご説明しましょう。たとえば、1GBの画像ファイルを、ファイル転送サービスで送るとしましょう。この場合、受信するコンピューターに1GBのデータを、そのまま丸ごと送ることはできません。1GBの画像データを、あらかじめ決めた約束事(プロトコル)に従って小さく分解した後、その小さくしたデータを転送先のコンピューターに一つずつ送って、元のデータに組み立て直しています。送受信のときに、
- どのようにデータを分解するか
- どうやってパケットを受け渡しするか
- どうやってパケットを組み立てて元のデータにするか
という決め事がプロトコルです。
ファイル転送サービスはパケットのやりとりを高速に行っているので、あたかも大容量のファイルを、まるごと一度に送っているように感じるわけです。
1-3 パケットの送受信は2人で声がけ確認しながら荷物を渡すイメージ
小さく分解したデータ(パケット)を送る作業は、人間がやるバケツリレーの作業のようなものです。2台のコンピューターが、「声がけ確認」をしながら、パケットを受け渡している姿をイメージすると、理解していただきやすいのではないでしょうか。
- PC-A
「これから1GBの画像データを送るよ」PC-B「了解。パケットに分解して送る準備ができたら教えて」
- PC-A
「分解終了。これから小分けしたパケットデータを送るよ」PC-B「了解」
- PC-A
「今、パケットを送るよ」PC-B「受け取った」
- PC-A
「次のパケットを送るよ」PC-B「全部受け取った。これから元のデータに組み立てる」
2台のコンピューターが、相互に声掛け確認しながら、小分けしたデータを最後の一つまでやり取りした後、元のデータに復元することで、大容量データを転送しています。
2. ファイル転送の代表的なプロトコルの種類と特性
実際に利用されているファイル転送で用いられているプロトコルには、いくつかの種類があります。以下に、一般的に使われているプロトコルを紹介します。
(1) HTTP(HyperText Transfer Protocol)
ホームページを閲覧する際に使うソフト(Webブラウザ)でよく利用されるプロトコルです。
(2) FTP(File Transfer Protocol)
ホームページの更新や、サーバーと呼ばれるコンピューターを経由して、データの送受信を行う時に使われるプロトコルです。ただし、パスワードなどの重要な情報を送受信する際は、セキュリティに不安があることが指摘されています。
(3) SCP(Secure Copy Protocol)
FTPと基本的には同じものですが、SSHという方法で、データを暗号化して送受信する方法を取っています。そのため、パスワードなどといった重要なデータを、安心して転送することができます。
(4) SFTP(SSH File Transfer Protocol)
SCPと同じく、データを暗号化して送受信するセキュリティが高いプロトコルです。
SCPとSFTPの違いは、スピードと、転送の再開ができるかできないかです。SCPは、データの転送スピードは速いですが、中断した場合、データの転送を再開できません。SFTPは転送スピードがSCPに比べて遅いですが、データ転送を中断しても、転送を再開できる特徴があります。
3. まとめ
ファイル転送で、一般的に用いられている代表的なプロトコルは、
- (1)
安全性を重視しなければならない場合に利用すべきもの
- (2)
データ送受信のスピードを優先しなければならない場合に利用すべきもの
に大別できます。
一般的に、ファイル転送のプロトコルは、「安全」と「スピード」は比例しません。機密保持が求められる重要なデータを送るのであれば、時間がかかるものの、セキュリティが高いプロトコルを採用したファイル転送サービスを利用するとよいでしょう。
自社のファイル転送のシステムが、どのようなプロトコルを採用しているか、一度確認することも必要かもしれません。最適なプロトコルを使うことで、安全でスピーディーなファイル転送が実現でき、ひいては日常業務がさらに円滑になるでしょう。
ファイル転送・超入門 コラム一覧
- ファイル転送・超入門
- データ転送サービスを使う前に認識すべき「シャドーIT」の危険性
- ファイル転送サービス:押さえておきたい!5つの選定ポイント
- 無料ファイル転送サービスの落とし穴!情報漏えい対策
- ファイル転送に使われるプロトコルの役割と種類を理解する
- 大容量ファイルを送受信するならファイル転送サービスがベスト?
- 止まらないデータの大容量化。ファイル転送苦労していませんか?
- 大容量ファイル転送ソフト、操作性を重視することで得られる3つのメリット
- IoTデータ連携で気をつけなければならない4つのこと
- クラウドデータ連携の方法とは?
- HTTP通信でファイル転送? ISDNが終了する2020年問題
- FTPでは解決できないファイル転送を実現するMFT
- USBメモリはもう不要?LANでデータ転送を行う3つの方法
- データ連携基盤で業務の効率化!3つのメリット
- 便利! ブルートゥースでのファイル転送活用術
- 知っているようで知らなかったファイル転送サービスの使い方
- データ連携ミドルウェアを選ぶときのポイント
- 業務効率化を推進するおすすめファイル転送サービス
- データ連携の頼れる味方!ETLによる効率的な変換と有効活用
- Salesforceとのデータ連携方法
- データ転送ミドルウェアで、もっと業務を効率的に
- これがおすすめ!セキュリティを意識したデータ転送サービス
- EAIによる効率的なデータ連携とサイロ化したシステムの統合
- 海外拠点とのシステム連携なら英語対応のツールで業務効率化!
- システム連携を一元管理することで得られる3つのメリット
- 社内に散在するデータ連携を実現するDIプラットフォーム