「月食」よりも「日食」の方が実は多い~あるいは「データを読む」ことについて考える
マーケティング部の渡辺です。
データやITなどに関する様々なことをゆるく書いているコラムです。
気になったニュースから:皆既月食がありました
今日は全世界的な時事ネタを話題にしてみました。
先日(2025/9/8)の早朝、数年ぶりの「皆既月食」があり世間的にも話題になりました。そこで月食について少し書いてみたいと思います。「そうなのか」と思える小話と、「データから必要な結論を出すことは難しい」という話などをします。
実は「次の月食はもうすぐ」(2026/3/3の夕方)なので、これを読んで知識を入れ知恵いただきますと、次の月食の時に「ちょっと賢い話」を周囲にできるのではないかと思います。
-
参考:月食について報じているニュース
⇒ 皆既月食2025 各地で神秘的な赤銅色の満月に<写真ギャラリー> - ウェザーニュース
「月食」と「日食」はどちらが多いでしょうか?
最初に、ちょっと「そうなんだ」と思える話から始めましょう。月食と同じような天体ショーとしては日食がありますが、果たして「月食」と「日食」どっちが回数の多い現象だと思いますか?
月食は数年に一回くらいで「なんか時々あるなあ」の感じで、日食は人生で一回見られるかどうか、みたいなイメージではないかと思います。でも実は、月食より日食の方が多いんですね。では具体的に、2020年から2025年での実際のデータを見てみましょう。
2020年から2025年の日食 ☼(11回)
- 2020年06月21日 金環日食
- 2020年12月15日 皆既日食
- 2021年06月10日 金環日食
- 2021年12月04日 皆既日食
- 2022年05月01日 部分日食
- 2022年10月25日 部分日食
- 2023年04月20日 金環皆既日食
- 2023年10月15日 金環日食
- 2024年04月09日 皆既日食
- 2024年10月03日 金環日食
- 2025年03月29日 部分日食
2020年から2025年の月食 ☽(8回)
- 2021年05月26日 皆既月食*
- 2021年11月19日 部分月食*
- 2022年05月16日 皆既月食
- 2022年11月08日 皆既月食*
- 2023年10月29日 部分月食*
- 2024年09月18日 部分月食
- 2025年03月14日 皆既月食*
- 2025年09月08日 皆既月食*
ご覧の通りに「日食の方が回数が多い」ことが解ります。直感と全然違いますね。
月食が全世界で観測できることが多い(その時間帯に昼ではない限り)のに対し、回数の多い日食ですが限られた地域でしか観測できないので、直感との乖離が起こっています。「*」を付けた月食は日本でも観測可能ですが(6回)、一方回数では多い日食は日本では一回も見えません(0回)。あるいはグローバル化だと言われますが、普段の我々は世界全体目線ではないらしいこともわかります。
月食と日食の仕組み
解っている人には今さらの説明ですが、月食や日食はなぜ起こるのでしょうか。「太陽」「月」「地球」の三つの天体の位置関係が以下のようになった時に発生します。
- 月食:「太陽から月に届く光」を「地球」が遮る
- ◦太陽→(地球)→月
- 日食:「太陽から地球に届く光」を「月」が遮る
- ◦太陽→(月)→地球
地球の方が月よりもサイズが大きいので、「月に落ちる地球の影」は月全体になることが多くなりますが、逆に「地球に落ちる月の影」は地球の一部だけになるため、日食が見えるのは限られた地域だけになります
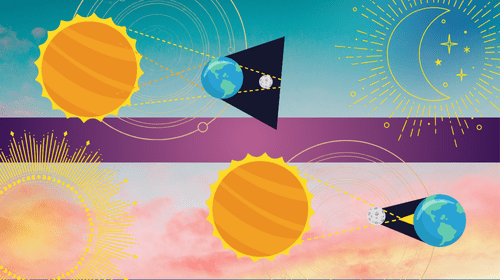
皆既月食で「赤い月」になる理由
皆既月食になると「赤い月」になりますが、これは「地球に大気があるから」です。波長の長い赤い光は大気によって屈折して地球の影の方まで回り込みやすく、結果月面は赤くなります。「波長の長い」ものが回り込む現象は、「光には影ができるが音波は後ろ側まで回り込むので聞こえる」とか「周波数の低い(波長の長い)800MHzのケータイの方が、電波が回り込むので圏外になりにくい」と似た現象。「月が赤い」のは実はこれらと似た仕組みによるもの。
美しい皆既日食が観られるのは「今が奇跡のタイミング」だから
また、皆既日食の時には美しい太陽コロナが見えますが、これは地球から見て、「月と太陽がほぼ同じ大きさ」に見える「奇跡的タイミング」なので観測できる現象です。月は徐々に地球から遠ざかっていますから見た目のサイズはだんだん小さくなり、もうしばらくすると月は太陽を完全に隠せなくなり、「金環日食しか観察できなくなる」はずです。我々は今、地球の日食事情的には「奇跡の時代」に生きています。
以上は次に月食が起こった時にでも、話のネタにしてください。
再度:本当に「日食の方が多い」のか?
というわけで「実は日食の方が多い」話をしましたが、どうもモヤモヤしている人もいるかもしれません。次はそのモヤモヤを話題にします。
このテキストは「ちょっと面白い小話をしますよ」として書き始めました、「面白い小話」としては「実は日食の方が多いんですよ」が期待に沿ったストーリーです。ただし、「でも月食は見えるけど日食は日本では見えないよね?見えないと意味ないのでは?」と言われれば、それもその通りです。
例えば社長から、「月食か日食を見に行く社内旅行を計画したら楽しそうだ考えているんだけれど、どっちの方が回数的に見込みがあるの?」と聞かれて「日食の方が回数が多いです」と答えたら「実際に見れなきゃ意味ないでしょ」と怒られるでしょう。
データを解釈することの難しさ(データの読み方は一つではない)
これは、一種の「データを解釈することの難しさ」の話でもあります。
- データを用意:月食がいつ起こるかデータ、日食がいつ起こるかデータ
- 質問:月食と日食、どっちが多いの?
つまり、この問いは「答えが一つではない」のです。同じデータの読み方が、文脈やニーズで異なることがあります。
もし、違和感なく読み進めていただいていたなら、実は皆さんは「私の言わんとすることを察して、空気を読んでいた」ことになります。場合によっては、その「空気を読んでしまう能力」が間違いを生むに思い込みになることもあります。また、「月食が多い派」「日食が多い派」がともに「俺たちが正しい」と言い張ってしまい、思い込みが喧嘩を起こしてしまうことだって起こるかもしれません。
あるいは上司から、「月食と日食、どっちが多いの?」とだけ聞かれたら、質問の意図を確認しなければいけないことになります。あるいは自分が上司なら、そんな質問をしたら部下は「上司の頭の中当てクイズ」になってしまうということ。空気を読めとか、言わなくても察しろとか言っていてはだめで、ちゃんと「なぜ聞いているのか」は伝えなければいけません。
本当はもっと難しいデータの解釈
それでは「社内旅行を計画したい」話だったら、日本で観測可能な日食や月食のデータを取ってきてコピペして報告すれば万全か、というと実はそうではありません。
考えてみてください、天文台が「日本で観測可能」だと言っていても、それは日本の領土のどこか一か所でも見える場所があると言っているだけです。例えば、太平洋の絶海の孤島でだけ日食が見えるだけなら、「社員旅行で観に行く」のはちょっと大変すぎるはずです。
やはり「質問の意図」を聞かねばなりません。そして例えば、「東京から数日程度の日程で現実的に社員旅行で行けるのか?」であるなら、判断に必要なデータが不足しており、新しいデータも必要になります。
- 追加で必要になるデータ
- ◦日食が観られる地域の緯度経度的なもの
- ◦その地域への東京から移動時間、交通費、費用など判断に必要なデータ
しかしながら、最初からここまで考えが至るかというと、そうではないはずです。データを分析し、何を報告しなければいけないか考えているうちに「もしかして、現実的に移動できるのかも調べないといけないのでは?」と気が付くことの方が多いはずです。
つまりデータ分析では、最初には必要だと思ってもいなかったデータが追加で必要になることがあります。
- データ分析やデータ活用では、後になって「あのデータも必要だ」となりやすいので、必要に応じて多種多様なデータを取得して利用可能にできる環境が必要
- ◦ノーコードで多種多様なデータやITシステム、クラウドサービスに自在に連携できる、弊社の「つなぐ」技術を利用ください。
考慮漏れはないのか確認する必要があり、漏れはよくある
そういうわけで、現実的に移動できるのかも合わせて分析しました。でも、本当にそれで万全でしょうか。人はミスをしやすく、抜け漏れもしやすい存在です。そういうことも踏まえて、ちゃんと「これで大丈夫なのか」確認をする必要があります。
それで他の人に意見を聞いてみることにしました。やっぱり考慮漏れがありました。実際に月食を楽しみにしたことがある人ならわかるでしょうが、「せっかくの天体ショーなのに天候が良くないので観られない」ことがあります。つまり、天候も気にしなければいけないことが解りました。
- データ分析やデータ活用では、後になって「あのデータも必要だ」となりやすいので、必要に応じて多種多様なデータを取得して利用可能にできる環境が必要
- ◦弊社の「つなぐ」技術を利用ください。
未来の天気予報はありませんが、晴天の多い月かどうかくらいは判断できます。しかしそのためには「追加のデータ」がまた必要になりました。
さらに考えてみると、「現地が晴天でも経路がダメ」なこともあります。離島で日食を見る予定だったとして、海が荒れていて航路が止まりやすい季節だったらよくありません。
ソフトウェア開発でソフトウェアテストが必ず必要であるように、抜け漏れの確認は必要になりますし、そのたびに追加のデータが必要になったりします。さらに考えてみると、人数分の宿が確保できそうなのかとか、国外なら現地が政情不安じゃないか?みたいなことも考えないといけない感じもあります。
- データ分析やデータ活用では、後になって「あのデータも必要だ」となりやすいので、必要に応じて多種多様なデータを取得して利用可能にできる環境が必要
- ◦弊社の「つなぐ」技術を利用ください
「全然別の切り口」
何も考えずに「日食の方が多いです」と回答すれば無配慮ではあるものの、ここまで配慮してレポートを出したら、とても配慮の行き届いたレポートになるでしょう。
ただこれでもまだ考慮ができていないことがあります。そして、世の中でイノベーティブな取り組みみたいに言われることは、通常の考慮の範囲外に飛び出すものだったりします。本件だと悪天候でも「飛行機で空を飛んでいれば」観測できるので、「飛行機から日食や月食を観ようツアー」なら天気や場所の心配は一気に減ります。
データ分析から新ビジネスが生み出されるようにしたい、みたいなことが割と気軽に言われますが、これくらいまで考えないと「分析の結果、新ビジネスが発見されました」にはならないという話かもしれません。
- データやクラウドの思わぬ組み合わせからの、思わぬ新ビジネスが発見のためにも、弊社の「つなぐ」技術をご利用ください
セルフサービスBI
考慮漏れに気が付いた、気になる関連事項に気付いた、あるいはなにかアイディアを思いつくたびに、だれかに聞きに行くとか、データの集め直しやデータ分析のやり直しを依頼書を書いてエンジニアに依頼していては、その都度手間と時間がかかってスムーズに進みません。
- これを素早く回せるかどうか:思いついた→自分で必要なデータを取ってくる→自分でデータ分析をやり直してそこから新しいことをすぐに理解する
つまりデータ活用の時代とは、「自分でやる必要がある時代」ということ。だから今では判断を下す人、例えば経営者なんかでも、可能ならば自分自身でデータを取り扱えることが望まれます。
もちろん、経営者がPythonをマスターしてデータ分析システムを自分で開発実装する、みたいなことはなかなか現実的ではないことが多いはずで、そうなると「現場の人でも自分で使える程度のもの」で必要なことができる環境を整備されることが望まれることになります。
このような環境整備はセルフサービスBIツールの整備だけでは不十分です。なぜなら、分析に使うデータの用意も必要だからです。そこで、分析に必要なデータを「自分たちで用意できる」手段も必要になります。ノーコードで多種多様なデータに連携して持ってくることができる、弊社の「つなぐ」技術はそういう時に必要になります。
-
▼弊社の「つなぐ」技術について詳しくはこちら
⇒ 日本発iPaaS(データ連携プラットフォーム) HULFT Square - ⇒ データ連携プラットフォーム DataSpider Servista
デジタルツイン:どうして未来のことが精密に解るのか
もう一つ考えたいのは、「なぜこんなに精密に日食や月食の未来予測がなされているのか」です。例えば天気予報、明日の天気くらいならかなり的確ですが、一か月先の具体的な日の天気となると予報には頼れません。しかし日食や月食、何十年も先まで「この日の何時何分に起こります」と正確に予測されています。
例えば日本で次に日食が観られる日は、2030年6月1日ですが、日食の開始から終了までがなんと「秒単位以下の精度」で予測されています。
特に日食については、過去も未来も非常に正確に予測できるようになっています。よく考えてみると結構とんでもないことです。
精密な観測と、過去からの蓄積と、完成された科学理論
データ分析では、とにかくデータを溜めろとか言われたりします。日食や月食は派手な事件なので、古代から長い間「いつどこで起こったか」は延々と記録されてきました。しかし、データ(いつ起こったかの記録)を大量に集めただけでは、今日のような精密な予測はできませんでした。
天体観測技術が発達し、天体の運動を計測できるようになってくると、月の軌道と太陽の軌道が重なると日食が起こるようなことが解るようになってきます。より精密に計測がなされて計測データが集まるようになると、発生の仕組みやある程度なら予測も可能になってきます。
精密な予測を可能にしたのは、物理学の進歩です。ニュートン力学により天体の運動を数式で説明することが可能になって一気に正確な予測ができるようになります。しかしそれでもなお「原因不明の予測誤差」が残っていましたが、アインシュタインの相対性理論によってそれも説明されるようになり、今や「正確無比な予測」が可能になりました。
デジタルツイン
計測データを基にして、現実の予測が精密にできるようになったとはつまり「デジタルツイン」が出来上がった状態であると言えます。もはや、現実の天体を観測せずとも太陽系の惑星が今どこにあるのかは正確に予測でき、遠い未来に起こる日食すら秒単位で予測可能になりました。
漫然と記録してデータを集めるだけではなく、精密なデータを集めることが重要であること、それだけではなく理論や数理的なモデルを作ることにより高度な成果が得られている例だと考えることができます。「天体のデジタルツイン」を完成させたのはアインシュタインでした。同じく、高度な機器の故障予測などを実現するためには、ただデータを集める以上の取り組みが必要であり、あるいはデジタルツインのような取り組みができると何が良いの?の例として「恐るべき精度で予測できるようになっている日食」が挙げられるかもしれません。
過去についても精密に解るなら
日食がいつどこで起こるのか、未来だけではなく過去についても精密な予測が可能になることで、副次的にいろいろなことも解るようになっています。
古代の文献に「日食があって国中が騒動になった」と書いてあるなら、日食は精密に予測できるため、「古代の暦における何月何日が具体的にいつのこと」なのか正確に解ったりします。また、位置がはっきりしなかった古代都市がどこにあったかを判断する手がかりになることがあります。
他社には想像もつかないほどに何かを精密に予測できるようになったことから、さらに自社だけが別のことまでわかるようになりはじめた。DXとか言われますが、どうせならこれくらいまでのことをしたいものです。
現場にも行こう
これを書いたのは、私が月食に興味を持っていたからですが、どうして興味を持ったのかというと「思いもよらないことで月食が素敵だったから」でした。
月食、実際に見たことがあるでしょうか。派手な現象が起こる皆既日食とは異なり、「月が微妙に欠けてゆく」あんまり派手ではない現象が起こり、最終的には「噂に聞くブラッドムーン」を目にすることはできます。でも、映画とかに出てくる「心象風景の大きな月」とは異なって、現実の夜空の月は「思ったより全然小さく」ビルに隠れたりしてよく見えなかったりします。
スマホで撮影しても、カメラが本当にすごい一部端末を除くと「なんだか微妙な感じ」になりやすいと思います。月は確かに赤いね、でも「ふーん」くらいなところもあります。
でも、実際に月食を観に行って気が付いたのは、もっと別な素敵さでした。大の大人が街角に集まって、みんなで空を眺めている。そんな街中の人々が素敵でした。皆既月食になって月が赤くなると小さい子供が喜び、みんなが一緒に空を見ている。今日はみんなが楽しくする日。
以前の月食でそう思って、それ以来、月食はいいものだと思うようになりました。現地にいかないと(私にとっての)「本当の月食の良さ」はわかりませんでした。しかし今回は、
- 皆既月食は月曜早朝の深夜2時半~4時と新聞配達みたいな時間帯
- 月の高度が低いためビルなどで盛大に遮られ、見える場所を探すのが本当に大変で気軽に見られるわけではなかった
というわけで、わざわざ夕方から寝て備えたのですが、今回は素敵な風景はなく、孤独に赤い月を眺めていました。現地に行くと気が付くことは本当にあります。
次の月食はなんと「来年のひな祭り(2026/3/3)」
というわけでここまで読んでいただいたことにより、皆さんにも月食知識が無駄につきました。そして、その知識を披露する機会が、間もなくやってきます。
- 次の皆既月食
- ◦2026年03月03日(なんとひな祭りの日)
- ◦日本全土で観られます
- ◦月食は18時49分から22時17分
- ◦皆既月食(赤い月)は20時4分から21時3分
3月だから晴れている可能性も高いはずですし、時間帯も素晴らしいです。きっと当日の街角には、揃って空を眺めている大人が並んでいるはずです。
当日は「ひな祭り」ですし、ひな祭りで月食なんて人生で一回しかない事件です。さらには説明した通り「月食は全世界的なイベント」なので、(月食が夜の時間帯の国なら)海外の人とも月食を楽しむことができます。
どうぞ当日、今覚えたことで小話をするとか、あるいは月を見ている人々が素敵だと思ってみるとか、あるいは精密な予測すらできるようになった人類の叡智について想いを馳せてみるとかしてみてください。私はまたきっと月食を観に出かけていると思います。あとは当日が晴れていることを願うばかりです。
執筆者プロフィール

渡辺 亮
- ・マーケティング部 デジタルマーケティング課 所属
- ・2017年 株式会社アプレッソより転籍
- ・大学で情報工学(人工知能の研究室)を専攻したあと、スタートアップの開発部で苦労していました
- ・中小企業診断士(2024年時点)
- ・画像:弊社で昔使われていた「フクスケ」さんを私が乗っ取りました
- (所属は掲載時のものです)
ITとビジネスの今どきコラム 一覧
- なんで「紙に書いて投票する」のか ~ITと「安全安心」について考える
- 学習データの増加が限界に到達した「生成AI/LLM」は今後どうなるのか?
- 不景気の時こそ「すごく売れる」商品があるって知ってました?(世の中何でもチャンス)
- AWSは、「どんなものもいつでも壊れる前提」で作られている
- 社会インフラの事故が相次いでいるのはどうしてか考える~これから再評価されるかもしれない「安全安心」
- 「核融合」と「錬金術」が合体した未来がやってくる?~「つなぐ」ことの可能性を考える
- 「月食」よりも「日食」の方が実は多い~あるいは「データを読む」ことについて考える
- 「源氏物語」にも「データ分析の話題」がある
- 「新潟の四大ラーメン」はどうして生まれたかの話~「新しいこと」とは”現場の試行錯誤”の中から生まれたりするもの
- 「奇跡みたいな逆転劇」は本当に起こることが(結構)ある~カターレ富山の奇跡のJ2残留劇について

