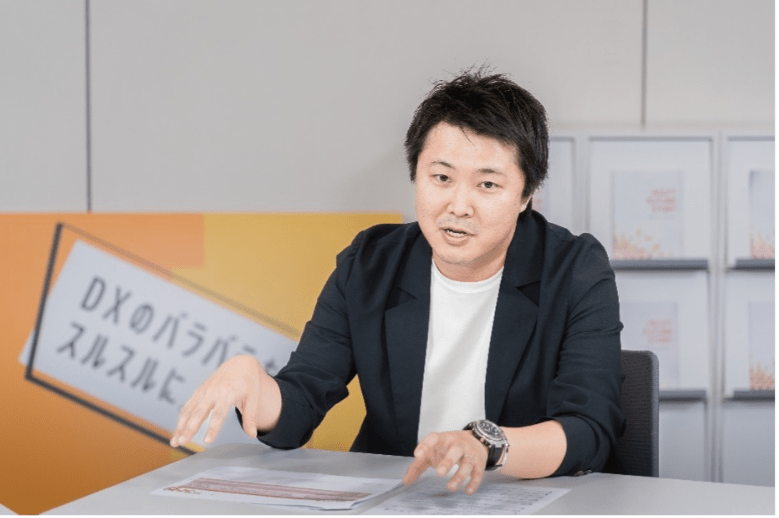市場で認知度を高めていたHULFT、
外からの気になる見え方
開発に至る経緯をお聞きしましたが、2006年に樋口さんが、2011年に宇佐美さんが入社されたと伺っています。そのころのHULFT自体はどんな状況だったのでしょうか。
樋口世の中のITシステムに詳しくない多くの学生同様、私も入社した時にはHULFTを全く知りませんでした。ただ、入社後数年経ったころ同じ業界で働いている友達のなかでも少し知られた存在となっていて、自社でHULFTを使っているという話も耳にする機会が増え、改めてすごいプロダクトだということをその時に実感したのを覚えています。
宇佐美私もセゾングループという名前に惹かれて入社したくちで、HULFTは全く知らなかった。正直に言えば、入社した当時は、”HULFTはもう終わり”みたいな雰囲気が漂っていました。ちょうど新たなデータ連携のプロダクトが登場したばかりで、そちらに注力していくという流れもありました。私の配属先はHULFTのメインフレーム版を開発しているチームでしたが、当時の役員から"HULFT、しかもメインフレーム版チームに新人を入れてどうするつもりだ"と言われたことも。
HULFTへの配属を希望していたわけではなかったのですね。
宇佐美ただし、当時の人事部長からは「あなたには絶対にHULFT開発に適正があるから、配属希望は無視して配属先を決めさせてもらった」と言われたことを覚えています。そこまでいうのであれば、自分の目で確かめてみようとHULFTに携わったところ、まさにドンピシャだったんです。長く愛されるプロダクトを成長させ続けることもそうですし、当時20代でアセンブラでコーディングできるエンジニアがほぼいない中、メインフレームというミッションクリティカルな分野で開発ができるということが非常に合っていたと思います。当時はHULFT7として、ミッションクリティカルな場面でお使いいただくため、「安全・安心」をテーマに、セキュリティ強化やJ-SOX法対応といった企業ニーズにマッチした機能を追加していました。
樋口HULFT8を企画する際に、実は大きな転機がありました。当初は新たなデータ連携プロダクトにHULFTを統合しデータ連携基盤化する計画でした。その企画ができた時点で、ユーザーの皆さまにお集まりいただき、ラウンドテーブルミーティングなどでご意見をお聞きしました。そこでは、確かに新たなデータ連携プロダクトもいいかもしれないが、HULFTという素晴らしいツールをさらに成長させて欲しいと多くの方からご意見をいただいたのです。弊社に求められているのは、あれもこれもできるというツールではなくHULFTで提供される安全安心でした。そのご意見を聞いた時、HULFTのまま進化を続けるべきだという考え方に傾いていったのです。
そんな折、DataSpider Servistaを持つアプレッソと業務提携する話が出てきました。今からETLを一から育てていくのではなく、すでに育っているプロダクトとともに、データ連携とファイル転送どちらもおさえていくという戦略に切り替えたのが、2014年のまさに大きな転換点でした。
お客さまからHULFTがいかに愛されているというのが分かった瞬間ですね。
樋口メインフレームとオフコン、そしてオープン系を連携させる際、仮にFTPで失敗するとリトライが大変だったり、連携するためのすり合わせに時間もかかったりしていた経験を持つお客さまが多い。ラウンドテーブルミーティングでは、HULFTを使うと迅速かつ確実に連携ができるようになって感動したと教えていただきました。改めてHULFTの凄さを実感したのです。