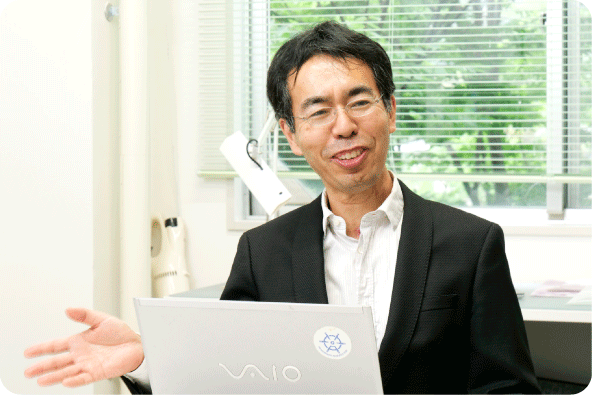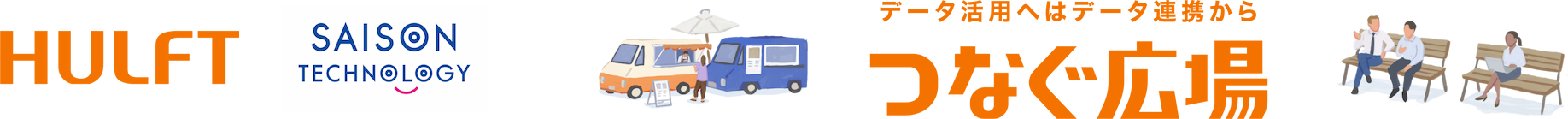大切なのは「分析結果がどう役立ち、どこまで責任を取れるか」
大切なのは「分析結果がどう役立ち、どこまで責任を取れるか」
第一人者が語る、ビジネス改革の手段としてのデータサイエンス


▼河本薫氏のプロフィール
大阪ガスにおいて、分析専門チームであるビジネスアナリシスセンター所長として数々の業務改革を成し遂げ、現在は滋賀大学データサイエンス学部教授として後進の育成にあたっている河本薫氏。その多大な業績は社会的に大きな注目を集め、2013年に「日経情報ストラテジー」が選ぶ「データサイエンス・オブ・ザ・イヤー」を、2021年に厚生労働省が選定する「卓越した技能者(現代の名工)」を受賞しています。
※役職や所属は取材時のものです。
そんなデータサイエンスの第一人者は、いかにして誕生したのでしょうか? また、日本企業のデータ活用の現状をどう分析し、今後をどのように見通しているのでしょうか? 河本氏にお話をうかがいました。
米国留学で叩き込まれた“数字に対する責任感とマナー”
データサイエンスの第一人者「河本薫」という人物がいかにして形作られたのか、関心のある人は多いと思います。データというものに興味を持ったきっかけや、数理工学を専攻した理由など、少年時代や学生時代についてお話しいただけますか?
私の若い頃については、話してもあまり絵にならない気がします。というのも、幼いときの体験や学生時代の勉強があったからこそ今こうなった、という必然性がまったくないからです。データに特別関心があったわけではなく、数理的なことはおもしろいかな、という程度の漠然とした理由で大学と専門を選び、単位を取って卒業しなければならないから勉強しました。
就職に関しても同様です。バブル期だった当時は学生の価値観も派手で、企業名と給料で会社を選ぶ人が多い中、私は単純に関西に残りたかったとか、会社訪問で社風のよさを感じたとかいう、やはり漠然とした理由で大阪ガスを選び、明確な目的を持たないまま入社しました。
当時は、「データサイエンティスト」という言葉はもちろん、データを活かした専門職自体、保険会社のアクチュアリー(保険数理士)ぐらいしか世の中に存在せず、そもそも専門を仕事に活かすなど想像すらできなかったのです。
データサイエンティストという専門職が注目を集めている昨今とは、まったく違う状況だったわけですね。
はい。結果的に今このようになったから、数理工学を勉強しておいてよかったな、と思うだけで、大学卒業までの人生が今につながった、というわけでは全然ないのです。のちほど話しますが、卒業後、ごく普通の人間として運命に振り回されながら、自分なりに一所懸命に生きてきて、気がついたらこうなっていた、という感じです。
失礼ながら、自分が子どもや学生だったときとあまり変わらないな、がんばれば河本先生のようになれるのかもと、ものすごく親近感が湧くというか、勇気をいただけるお話です。
そういっていただけると嬉しいです。ともかく、そういう経緯で私は大阪ガスへ入社して、家庭用ガス冷暖房機を開発する部署に配属されました。その頃、ガス会社にとっての悲願は、暖房用として冬にしかたくさん売れなかったガスを、夏にも売れるようにすること。ガスを利用した冷房は業務用や産業用では実用化されていましたが、家庭用として実用化されていなかったのです。それを世界で初めて作るというのが、私に最初に与えられた任務でした。
ところが私は、それまでコンピュータしか触ったことがなく、工具を使って機械をいじるなんてまったくやったことがありませんでした。それでも試作機を作って、これでもかというぐらい実験を繰り返さなくてはならず、本当に苦労しました。周りは機械工学科の出身者ばかりですから、数理工学をかじってきた人間として自分の存在意義を示すため、実験の空き時間にシミュレーションモデルを作ったりもしました。しかし結局、私の作った数理的なモデルなんて、機械工学科出身の先輩たちの洞察力には絶対に勝てないわけです。
試行錯誤されたのですね……。
それで入社3年目のある日、上司からこういわれたのです。「機械工学科では、数式なんて使わなくても、理屈なんてなにもわからなくても、世の中に役立つものを初めて作ったら博士号をもらえるんだよ」と。その言葉で、私の価値観は180度変わりました。データを使ってなにかがわかったからといって、それを活用できなければ意味がない、世の中の役に立って初めて価値があるのだ、と。それが私の人生における1つのマインドチェンジになりました。
それからは方法論にこだわらず、もっぱら役立つかどうかという観点から頭を使い、先輩たちには勝てないまでも、それなりに成果を上げられるようになりました。
ただ、当時の私はまだ“甘ちゃん”でした。両親に不幸があり、急に一人ぼっちになってようやく、「自分の力で食っていかなあかん」と強く意識するようになったのです。このままものづくりの世界に身を置いても、勝ち残っていく未来図を描けない。やはり自分の唯一の強みは数理工学を勉強したことであり、それを活かして食べていくしかないと、遅ればせながら考えるようになりました。
アメリカへ留学したのはそういうタイミングだったのですね。
はい。会社の海外派遣制度に応募して、1998年から2年間、アメリカのエネルギー省傘下の研究所であるローレンスバークレー研究所へ研究員として留学する機会を得ました。その研究所は普通、日本の大学教員が行くようなところで、私のキャリアからすれば留学などあり得ないことでしたから、本当に幸運だったと思います。
当時の私は、というより今もそうですけど、怖いもの知らずというか、なにも知らないがゆえに、こうしたいという思いが募るとそれを実現するまで諦められない人間なのです。アメリカ留学についても、同研究所の偉い人が来日するという情報をキャッチして、いても立ってもいられずに直接連絡を取り、なんとか会う約束を取りつけました。でも私には、PRできるようなデータ分析のキャリアがまったくない。それで、とにかく熱意だけでも示そうと、同研究所が出している論文を大量に入手して、読めたのはちょっとだけでしたが、全部紙袋に詰め込んで持っていきました。その上で、どうしてもそちらで仕事したいという思いを下手な英語で懸命に訴えたところ、奇跡的に熱意を認めてもらうことができたのです。それが私にとって人生最大のキャリアチェンジの始まりでした。
アメリカではどんな仕事に携わったのですか?
同研究所のミッションは、アメリカのエネルギー政策の立案を支援するためのデータ分析をすること。私にはデータ分析のキャリアが全然なかったので、最初は苦労しましたが、上司に恵まれて、いろいろと大きな仕事を任されました。それらを通じて、「数字に対する責任感とマナー」というものを徹底的に仕込まれたのです。
一例を挙げると、あるとき、石炭業界の雇ったコンサルタントが、「Dig more coal(石炭をもっと掘れ)」というタイトルのレポートを発表しました。当時は、インターネットが急速に普及し始めた頃。ゆえに今後、コンピュータによる電力需要が急増するから、電力不足を補うために石炭火力が必要だから石炭を掘れ、というのがそのレポートの趣旨でした。要するに石炭業界によるロビー活動なのですが、結果として電力会社の株価が上昇するなど、社会的に大きな影響が出始めたのです。それを見て上司が、「この数字はでっち上げだ。放置すると世の中が大変なことになる」と。レポートの数字が間違っていることを証明する仕事を任された私は、コンピュータ関連の電力消費に関するデータをできる限り集めて分析して、米国全体でのIT機器の電力需要を推計し、レポートの数字はやはりでたらめだと上司に報告しました。そのときに上司から、「自分の出した数字に対して本当に責任を取れるか?」と徹底的に追求されました。世の中に正しい数字を普及させるというゴールを目指す上で、決して忘れてはならないのは、数字に対する責任感と、誤解なく伝えるための表現のマナー。アメリカで叩き込まれたこの2つが、今の私の仕事につながる一番の“魂”になっています。
そうした経験によって、データサイエンティストとしての「河本薫」が確立されたわけですね。
アメリカでの経験が原点にあるのは確かです。ただ、そういう意味でいうと私のマインドは、「データサイエンティスト」ではなく「データアナリスト」なのです。多くのデータサイエンティストは、データをなんらかのモデルに突っ込んで分析結果を出します。でも、私の価値観だと、それだけでは受け入れられない。その分析結果にどういう意味があって、どう役に立ち、どこまで責任を取れるのか。それを明らかにしてこそ価値があると考えているからです。そしてその部分は、日本ではおろそかにされているのが実情だと思います。