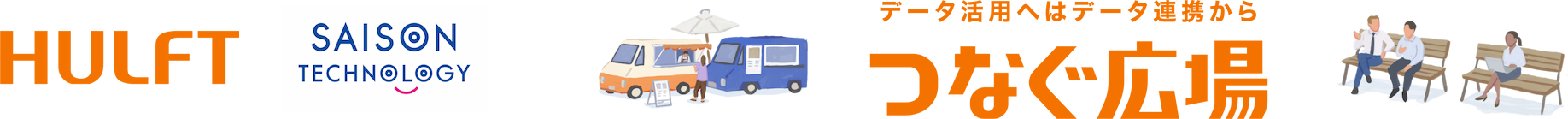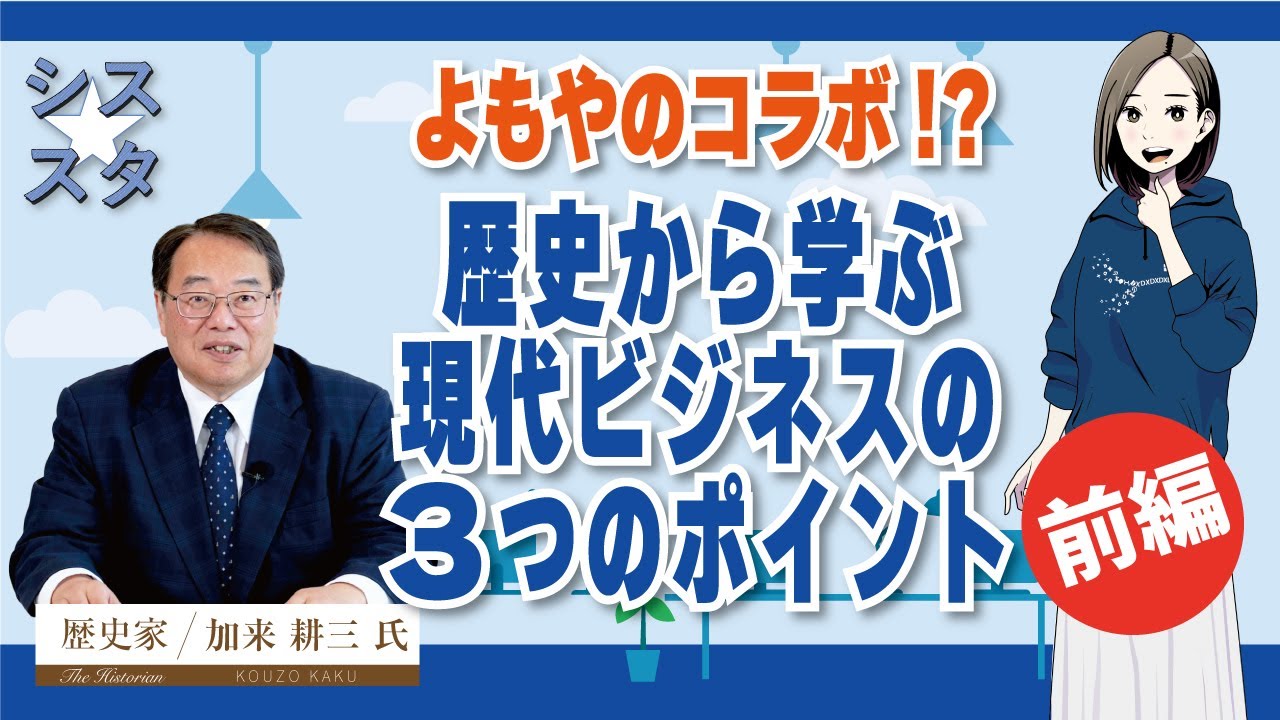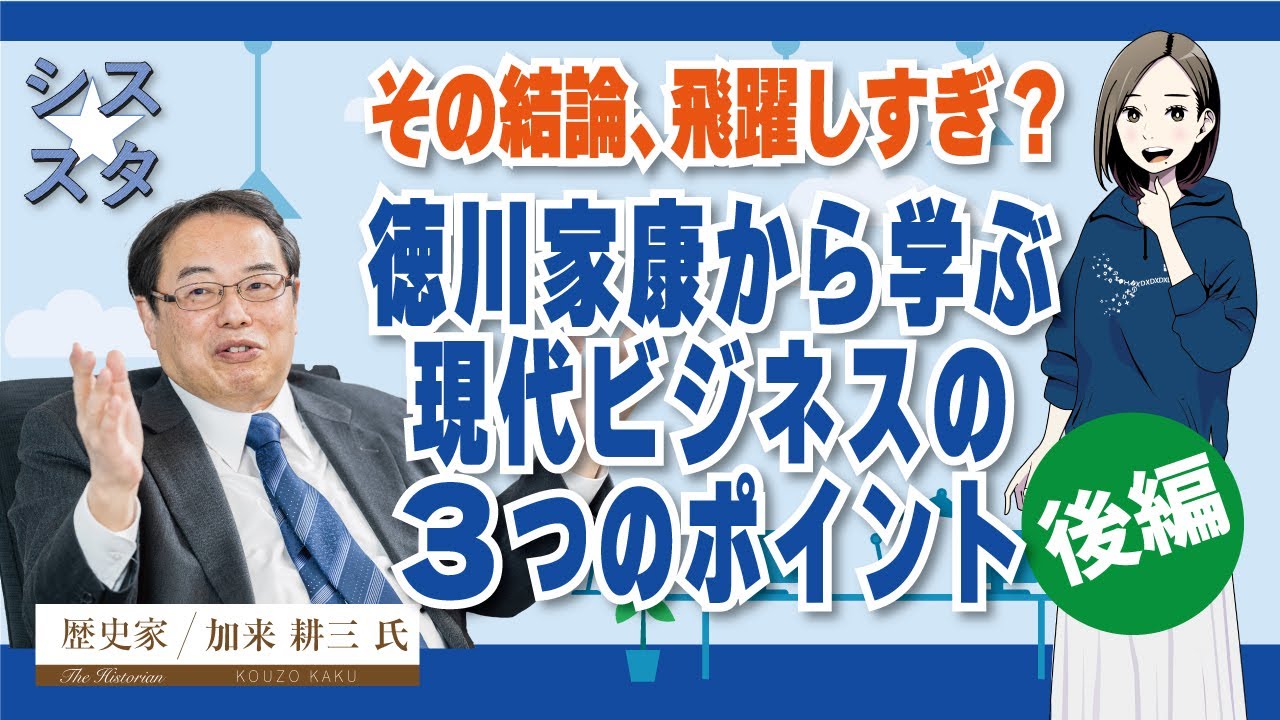三者三様の「情報戦略」でその名を残した紫式部・清少納言・和泉式部
三者三様の「情報戦略」でその名を残した紫式部・清少納言・和泉式部
~平安時代中期に女流文学が花開いた背景を探る~


『源氏物語』の紫式部や『枕草子』の清少納言、歌人として名高い和泉式部。今もなお人々に感銘を与え続ける作品を世に送り出した彼女たちは、平安時代中期のごく短期間に集中して出現した。この現象が偶然でないならば、いったいその背景にはどのような、できごとや人々の営みがあったのだろうか?
歴史家・作家の加来耕三氏は、「情報」をキーワードに日本の古代から中世の歴史を振り返ることで、その理由を説明できるという。紫式部や清少納言、和泉式部の人となりや人生に関するエピソードを交えながら解説してもらった。
▼加来耕三氏のプロフィール
奈良大学文学部史学科卒業。学究生活を経て、昭和59年(1984)3月に、奈良大学文学部研究員。現在は大学・企業の講師をつとめながら、歴史家・作家として独自の史観にもとづく著作活動をおこなっている。内外情勢調査会講師。中小企業大学校講師。政経懇話会講師。
・代表的著作(新刊)
『教養としての歴史学入門』(ビジネス社・2023)
『徳川家康の勉強法』(プレジデント社・2023)
『家康の天下取り 関ヶ原、勝敗を分けたもの』(つちや書店・2022)
・監修・翻訳等(新刊)
『読むとなんだかラクになる がんばらなかった逆偉人伝 日本史編』(監修・主婦の友社・2023)
『コミック版 日本の歴史 第87巻 結城秀康』(企画・構成・監修・ポプラ社・2023)
・その他
加来氏が解説をつとめる『関口宏の一番新しい中世史』(BS-TBS・毎週土曜昼12時)が放送中。
※役職や所属は取材時のものです。
平安中期の女流文学開花の土壌となった、“古代”の情報革命と政治体制の激変
これまでのインタビューで繰り返し話してきた通り、歴史学というのは、まず立ち止まって「なぜ?」という“問い”を持つこと、次に地に足をつけて「実際にはどうだったのか?」というプロセスを考えていくことが重要です。
たとえば、2024年の大河ドラマ『光る君へ』の舞台である平安時代中期を採り上げるなら、こんな疑問が湧いてくるでしょう。すなわち、『源氏物語』を著した紫式部をはじめ、清少納言や和泉式部などの傑出した女流文学者が、なぜあの時代に突然、大量に輩出されたのか、という“問い”です。
確かに、以前から不思議に思っていました。突き詰めて考えたことはありませんでしたが……。
では、今回はそれをテーマにしましょう。先にヒントをいってしまうと、キーワードは「情報戦略」です。あの時代に女流文学が一気に花開いた背景には、ある種の情報革命ともいえる日本の言葉や社会の大きな変化があり、またその状況を最大限に活かして良質な情報を集め、それぞれの求める方法でアウトプットできた、ある階層の女性たちの存在があったのです。
それはどういうことか、順を追って説明しますが、その前に1つ質問です。そもそも平安時代中期とは、歴史学の時代区分でいうと、古代ですか? それとも中世ですか?
学校では「平安時代は中世」と教わりました。
残念、外れです。日本史における古代・中世・近世・近代という分け方は、実は単純にヨーロッパの歴史学の時代区分に当てはめただけで、ヨーロッパとはずれがあるのですが、無理に当てはめると、後三条天皇が摂関政治に終止符を打ち、院政を始めようと考えた1072年から中世に入ることになります。そうすると、清少納言(966年頃~1025年頃)や紫式部(973年頃~1031年頃)、和泉式部(978年頃~没年不詳)の活躍した時期はまだ、古代ということになります(各々、生没年は諸説あり)。
つまり、『枕草子』や『源氏物語』は、それほど古い時代に書かれたものだということですね。
そうです。1966年にフランス・パリで開かれたユネスコの会議で、「偉人年祭表」が公表され、日本人で初めて、その中に入ったのが紫式部でした(ほか数名も選出される)。論評には、『源氏物語』が古代の人物によって書かれたとはとても思えない、というような選定理由が書かれていました。世界的に見ても、紫式部の長編小説『源氏物語』は稀有な作品だということです。ここでまた1つ、なぜ世界に先駆けてあのような作品を、しかも女性が書けたのか、という疑問が出てきますね。
謎がますます深まってしまった気がします……。
そのように、「なぜ?」「なぜ?」と次々に疑問が出てくるのが歴史学です。1つの疑問があって、考えてもわからないときには、その前の時代、前の時代へとさかのぼり、疑問に思う事象の起こりから結果へ至ったプロセスを考えていく必要があるのです。
話を戻しましょう。ご存じの通り、平安時代中期の女流文学は、漢字と平仮名を使って書かれています。平仮名は、漢字をもとに発明された万葉仮名をさらに崩す形で900年頃に成立したとされる、日本独自の文字です。女文字とも呼ばれるこの言葉がなければ、さらにいうなら日本語というものがなければ、『源氏物語』や『枕草子』のような作品の誕生は、おそらくなかったでしょう。とすると、そもそも日本語がいつ、どういう経緯で成立したかを考えることで、平安女流文学誕生の背景を1つ、明らかにできる可能性があるわけです。
前の時代へさかのぼって考えるのですね。
はい。飛鳥時代の天智天皇や天武天皇の頃、日本に文字はまだありませんでした。もちろん言語はあったでしょうが、大陸からやってきた人々の言葉、朝鮮半島の人々の言葉を、ほぼそのまま借用していたと考えられます。ところが当時、どうしても自国の言葉を記す文字を持たなければいけない、という危機感を日本の人々に抱かせる大事件が起こりました。663年の白村江(はくすきのえ、とも)の戦いで、日本・百済の連合軍が、唐・新羅の連合軍に大敗したことです。このまま自国の言葉を持たずにいれば、1つの国としてまとまれず、侵略されて相手国の体制に組み込まれてしまう、と初めて気づいたのです。
なるほど。それで、日本語をどのように作ったのでしょうか?
分解した漢字それぞれに日本の土着の言葉を当てはめ、意味を一字ずつ持たせていきました。ここで大事なのは、単に言葉を置き換えたのではなく、当時の日本の人々でもなんとか理解して使えるレベルにまで落とし込んだことです。文字の形や発音、意味合いなどの面で、人々にとってあまりに突飛なものを作ると、咀嚼できずに結局、使われません。実際、平仮名・片仮名が確立されるまでの過程では、たとえば同じ「あ」でも、さまざまな形に崩して書かれたり、いろいろな意味や音を与えられたりしながら、人々に合わないものは消えていったのです。
そうして日本語は、天武天皇の在位中(673年~686年)に作り始められ、次代の持統天皇の在位中(690年~697年)に完成したと考えられています。当時の日本の人々は、そういう国家的な事業を、ごくわずかな期間で成し遂げたのです。
言葉はまさに「情報」そのものですから、いわばとてつもない情報革命を短期間で実現させたということですね。
そうです。なぜそんなことができたかというと、必死だったから、という一語に尽きる思います。幕末のときと一緒で、日本人は尻に火がついたらがんばれる、逆に危機感がないと何もできないということです。
ともかくも、そうした経緯で平安時代中期に確立された平仮名が、女流文学の開花する1つの大きな要因になりました。そして、実は同じ時代にもう1つ、結果として平安女流文学を生み出す土壌となったと考えられる環境が、同様の経緯で整いました。唐から輸入した律令制が機能しなかった結果として始まった、摂関政治です。
白村江の戦いで破れた日本は、中央集権化を図り、一流国の形をとるために律令制を採り入れました。これは、朝廷を構成する豪族たちに既得権を放棄させることにほかなりませんから、先ほどの日本語誕生の話と同様、国の存亡の危機が迫って、初めて可能となったことでした。
ところが、そうして導入された律令制は、日本ではうまく機能しませんでした。なぜなら、もともと律令制というのは、科挙に合格した優秀な官僚が国を動かすことを前提に、中国の歴代王朝で作られたものであり、科挙のない日本には、律令に従って国を動かせるような能力の高い官僚が、そもそもいなかったからです。
科挙は世界一難しかったとされていますが、当時の日本のエリートとされる人が受けても合格できないレベルだったのですか?
この時代までの日本人の中で、科挙に通り得たのはおそらく、吉備真備と安倍仲麻呂ぐらいだっただろうと思います。そういう状況下で朝廷は、官僚不在という穴を埋めて律令制を機能させるための策として、参議・中納言・内大臣など、律令制に規定されていない「令外官」という官職を新設したものの、やはりうまくいきませんでした。そして最終的に苦肉の策として、摂政・関白という巨大な権力を持つ「令外官」を新設するに至ったのです。
ご存じの通り、そこから始まる摂関政治とは、藤原氏が子女を入内させて天皇の后とし、天皇の外戚として政治の実権を代々、独占した体制です。天皇の后となる子女は、当然、天皇に気に入られるために教養を身につけなければなりませんでした。
そしてそのとき、彼女たちを手助けできるほどの高い教養を持つ、いわば“家庭教師”としての女官の需要が一気に高まったのです。のちほど詳しく述べますが、平安時代中期に、紫式部や清少納言、和泉式部など、当時の並の貴族男性をはるかに超える教養と能力を持った女官たちは、そういう政治体制の変化の中から、必然的に現れた存在だということです。

清少納言・紫式部・和泉式部の人生に見る、三者三様の「情報戦略」
摂関政治に加えてもう1つ、律令制の機能不全を補う官職として設置され、女流文学者を輩出する土壌となったのが、「受領」と呼ばれる階層です。「受領」とは、諸国へ派遣される国司の最上位である「守」のことです。彼らは、各地方の長官として大きな権力を有していた一方、あくまで官位の低い地方官であるため、中央での栄達は望めませんでした。そして興味深いことに、紫式部や清少納言、和泉式部など、この時代の優れた女流文学者の多くが、この受領層の家から出たという共通点を持っていたのです(夫が「受領」の場合も)。
確かに、紫式部の父の藤原為時は越前守・越後守、清少納言の父の清原元輔は周防守・肥後守、和泉式部の父の大江雅致は越前守を務めていますね
中央官になれない人たちの娘の多くが、文学者になったのはなぜなのか? 家庭環境が共通の要因になったのだとすれば、それはいったいどのようなものだったのか? これは立ち止まって考えてみる価値のある“問いかけ”です。
たとえば藤原為時は、花山天皇に漢学を教えたほどの漢詩人、清原元輔も、『後撰和歌集』の編纂者の1人として名高い歌人でした。中級以下の貴族である彼らは、努力しなければ「受領」にはなれませんでした。同様に官位の低い受領層の中には、彼らのように能力を磨き、教養を身につける人が少なくなかったのです。
同時に彼らは、たとえどんなにがんばっても、決して中央には進出できないことを知っていました。ゆえに「受領」の中に、娘を教育し、摂関政治の中で需要の高まっていた天皇の后候補の家庭教師役として、自分の代わりに中央へ送り込もうとした人が出たとしても不思議ではありません。
紫式部や清少納言、和泉式部などは共通して、そういう向上心と教養のある教育熱心な父(母も同様の環境)を持ち、家に揃っている漢籍などの資料に好きなだけ触れて、当時もっとも重要かつ最先端の情報を得ることができました。だからこそ、男性を上回る教養を身につけ、創作の世界へ入っていくことができたのです。逆にいうと、摂関政治や受領層が律令制導入の結果として生み出されていなければ、彼女たちのような優れた女流文学者たちもおそらくは存在しなかったということになります。
ここまでを整理すると、平安時代中期に女流文学が一気に盛り上がった背景には、まず日本語の誕生という情報革命があり、さらには摂関政治によって教養のある女官が求められる状況の出現と、教養の習得に必要な情報に触れやすい受領層の形成があった、ということですね
そうです。要するに、女官たちが情報をインプットする環境と動機がこの時期にすべて揃った、ということです。もちろん、情報をどのように取捨選択し、どうアウトプットするか、という点については人それぞれでした。今回採り上げている紫式部、清少納言、和泉式部を比べてみても、性格や生育環境によって、そこに大きな違いが出たことがわかります。
たとえば紫式部。彼女は、学者肌の父のもと、蔵書を読み漁って漢学の教養や和歌の技法を身につけました。幼い頃に母を亡くし、少女時代に姉を失い、29歳で結婚した夫を3年後に病気で亡くすなど、愛情に関しては満たされない生活を送ったようです。
結果として彼女は、優しく柔らかな外面とはうらはらに、客観的で冷ややかな観察眼を持ち、内面的には世の中に対する無常観や強烈な自我、敵愾心を抱えていたことが、作品を通じてうかがえます。先に名声を博した清少納言をライバル視し、現代風にいえば「得意げに漢字を書き散らしているが、よく見ると間違いも多く、たいしたことはない」「行く末はろくなことにならないだろう」などと酷評しています。
そういう話を聞くと、現代にもいるようなタイプの人で、ちょっと親しみを感じますね。
仕事は猛烈にできるけれども、理屈っぽくうぬぼれが強い。やはりこれは学問、いい換えれば情報収集のプラス面とマイナス面がはっきりと出たケースといえると思います。紫式部は、徹底的な勉強、つまり情報収集によって、家庭教師として求められる教養はおろか、『源氏物語』を書けるほどの能力を身につけました。しかしその反面、当時の女性として持ってはいけない情報に多く触れすぎたために、普通の女性なら感じることのない不幸を抱えざるを得なくなったのです。情報のプラス面とマイナス面は表裏一体であるということを、紫式部の人生から学べるのではないでしょうか。
それに対して、清少納言はどういう人物だったのでしょうか?
清少納言は、紫式部とは正反対といっていい性格でした。外面的には強気で行動力がありました。女性が才能を磨くとかえって不幸になる、という思想が支配的な時代にあって、紫式部は漢字の「一」の字も読めないようなふりをしていましたが、清少納言はそういうことをまったく気にしませんでした。清少納言はあるとき、一条天皇の后である定子から「香炉峰の雪いかならむ」と問いかけられ、即座に御簾をすっと上げてみせることで応えました。唐代中期の詩人・白居易の漢詩の一句にそういう場面があることを知っていて、「私すごいでしょ?」とばかりにひけらかしたわけですね。情報をフル活用して、そういうあけすけなことをパーッとやる明るさが、彼女にはあったようです。
一方、清少納言は内面的には、鋭い感性と、天才的ともいえるような解説力を持っていましたが、同時に、「これでよかったのかな、悪かったのかな」と内心で、常に怯えているようなところもありました。まさに外柔内剛の典型という性格で、情報の活用の仕方もそれに沿ったものだったといえそうです。
では、和泉式部についてはいかがですか?
和泉式部の人生を眺めると、まさに自分のために世の中はあると考え、あらゆるものを利用して自分のしたいことをした女性だったと感じます。和泉式部は、母が冷泉天皇の后の昌子内親王の乳母を務めていたため、後宮で育ちました。後宮というのは愛欲にまみれた場所ですから、和泉式部はかなり早熟で、優れた容姿とも相まって、多くの男性と浮名を流しました。そのため、紫式部からは「人の道から外れている」などと評されています。
しかし、和泉式部自身は、「外れている」ことに対して悔いがありませんでした。保守的な人からどう思われようと気にしない。よくも悪くも欲望に忠実で、恋愛と、歌人としての感覚や技能を磨くことしか頭にないような人でした。それだけに、今回採り上げている3人の中では、もっとも感性が鋭く、情報感度も高い。歌の技法的には、漢学に通じている紫式部のほうが上だったかもしれません。しかし、歌というのは理屈ではありません。歌そのものから感じられる情熱や情緒は、和泉式部のほうが勝っていたように思います。実際、紫式部ですら、人間としてはともかく、歌人としては和泉式部を高く評価していました。
そのように3人を見比べると、情報の重要性を等しく認識して活用した一方で、情報を求める方向性とアウトプットの仕方といった戦略は、三者三様だったことがわかります。
そんな3人の人生から、現代のビジネスパーソンが学べることがあるとすれば?
忘れてはならないのは、平安時代中期に女流文学が花開く環境が整ったからといって、誰もが紫式部や清少納言のようになれたわけではない、ということです。ちょっと漢籍を読めるとか、和歌を詠えるというレベルでは、摂関政治のシステムにおいて求められる女官の役割は果たせませんでした。紫式部にしても清少納言にしても、漢学の知識は男性のはるかに上で、ありとあらゆる書物を読んで覚えていました。それぐらいの能力と向学心、それに努力がなければ、当時の男性中心の貴族社会では認めてもらえなかったのです。
そういう状況は、今の日本にも通ずるものがあると思います。対談や講演会でご一緒する女性経営者からお聞きするのは、日本社会で女性は、男性の2倍努力してもだめで、公私ともに4倍努力して、初めて対等と認められる、ということ。現代のビジネスパーソンは、その点では平安時代中期とそう変わらない今の社会のあり方について、改めて考えるべきではないでしょうか。
おすすめコンテンツ:e-book 武将からビジネス成功のヒントを学ぶ
このe-bookでは、戦国時代の知略を用いて、限られた情報を如何に活かすかというテーマで、徳川家康や伊達政宗の戦略を分析しています。彼らの判断力や情報活用法から、ビジネスにおける実践的なヒントを見つけ出し、成功に向けての新たな視点を手に入れましょう。興味のある方は、以下のリンクからぜひご覧ください。